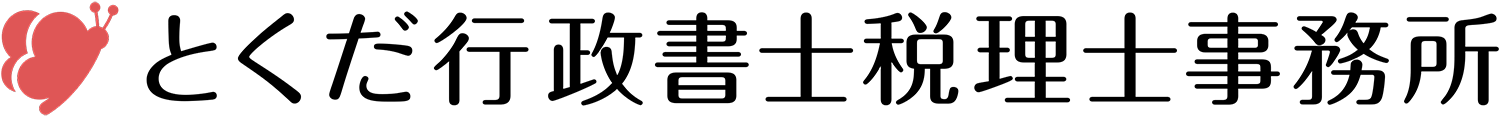自分が亡くなった後に誰かに財産をあげたいとき、主な方法として死因贈与と遺贈があります。
死因贈与は、死亡によって効力が発する贈与契約で、通常は相手方と贈与契約書を取り交わします。
遺贈は、遺言によって他人に財産を無償で提供することをいい、遺言書を書く人が単独で行うことができます。
自らの財産を他人に与えることを指定しておくという意味ではどちらも同じですが、両者は法的性質が異なります。
死因贈与はあまり知られていないため、遺言書を書く人が多いように思います。
でも、場合によっては、死因贈与のほうが適していることもあります。
今回の記事では、遺贈よりも死因贈与、つまり、遺言書よりも死因贈与契約書を作ったほうがいいケースについてまとめました。
ケース1
贈与を取り消される心配があるとき
遺贈は、遺言書を撤回することにより、遺言者が一方的に取り消すことができます。
死因贈与も取消は可能ですが、あげる側ともらう側の双方の合意が必要なので、取り消しのハードルは遺贈よりも高いです。
対象が不動産であれば、死因贈与では仮登記が可能です。仮登記が抑止力となって取り消されにくいということもあります。
ケース2
遺産をあげる見返りに、生前に世話をしてもらいたいとき
死因贈与では、生前に面倒をみてもらう見返りとして、死後に財産をあげる約束ができます。
遺言で負担付き遺贈をすれば同じようなことができますが、知らぬ間に遺言が撤回されている可能性があり、世話をする側が疑心暗鬼になってしまう場合があります。
死因贈与の場合、負担付き死因贈与契約の負担部分の履行が生前になされていれば、贈与の撤回は制限されます。ほぼ確実に財産をもらうことができるため、世話をする側も安心できます。
ケース3
遺産の受取りを拒まれる心配があるとき
遺言書による遺贈では、受遺者はいつでも遺贈の放棄ができます。
一方、死因贈与契約では、贈与者の死後、受遺者は贈与を取り消すことができません。
遺産を確実に受け継がせたいという理由で、遺贈ではなく死因贈与を選択することがあります。
ひとこと
死因贈与がいいか、遺贈がいいかは、遺言書で叶えたい希望により違います。
場合によっては税金面についても考慮する必要があります。
どちらがいいか迷ったら、相続を扱っている行政書士や弁護士、司法書士に相談しましょう。
公正証書にするのであれば、公証役場の公証人さんにも相談できます。