面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
相続放棄の念書は無効!法律的にも税務的にも意味がない理由を税理士が解説

相続の相談をしていると、家族に相続放棄の念書を書かせて安心している方が少なくありません。
しかし、念書には法律上も税務上も効力がありません。
この記事では、法律の仕組みだけでなく、税理士の立場から見た税務上の影響まで踏み込みます。
「相続放棄の念書は無効」という話は多くのサイトでも触れられますが、
相続税法上の扱いや贈与税リスクまで解説しているものは少数です。
法と税の両面から、現実的な対処法を整理していきます。
生前の「相続放棄」は法律上できない
相続放棄とは、亡くなった方の残した財産を、プラスの財産もマイナスの財産も含めて相続しないことをいいます。
この手続は、家庭裁判所に申述して行うもので、相続が開始してからでないと行うことはできません。
根拠は民法第915条・第938条および家事事件手続法第201条に定められています。
したがって、生前に「相続放棄します」と書かせても、その念書には法的効力が一切ありません。
あくまで心理的な抑制効果にとどまり、法律的には何の拘束力も持たないのです。
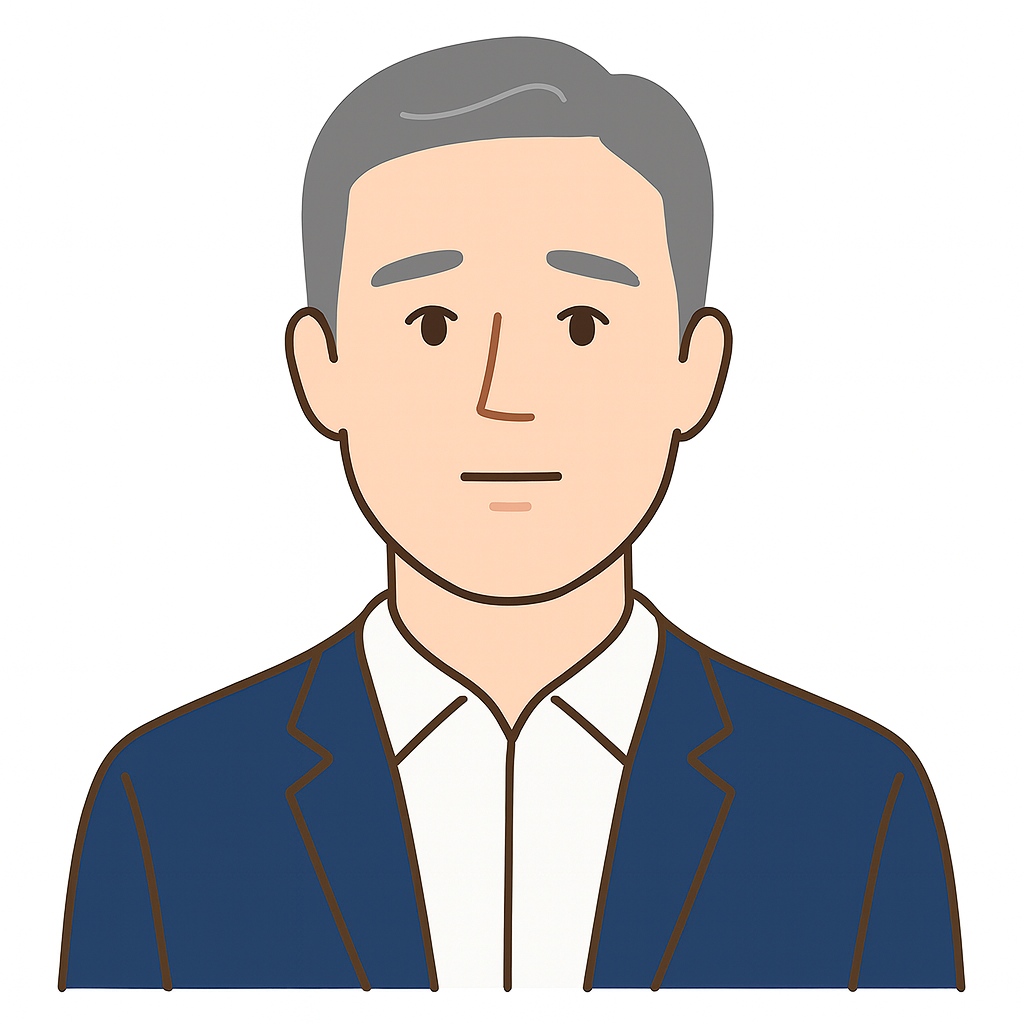
生きているうちに「相続しません」と書かせておけば安心だと思っていました。



相続放棄は“亡くなってから”でないとできません。生前の念書はあくまで気持ちの確認であって、法的な効果はないんです
💡税務の視点:念書では相続放棄とみなされない
税務上も、念書だけでは相続放棄をしたことにはなりません。
むしろ、念書を理由に生前に財産や金銭を渡していた場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。
たとえば、
「将来の相続では何も受け取らない」という念書を書かせる代わりに、
親がその子へ金銭や不動産を与えた場合、
その行為は相続放棄の見返りとしての贈与とみなされ、
贈与税の課税対象となります。
放棄の意図があっても、税務では形式よりも実質を重視するため、
「念書を条件に財産を渡す=生前贈与」と判断されるのです。
相続開始後に念書を持ち出して「この人は放棄した」としても、
税務上は相続放棄が成立したとはみなされません。
相続税法第15条は、遺産に係る基礎控除額と相続人の数の計算方法を定めており、
そこでは明確に次のように定められています。
相続税法第15条第1項・第2項
「遺産に係る基礎控除額は、三千万円と六百万円に相続人の数を乗じて得た金額の合計額とする。」
「相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とする。」
このため、生前の念書による放棄は税務上も無効であり、
相続税の計算ではその人を法定相続人としてカウントする必要があります。
基礎控除の計算は
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で行い、念書の有無にかかわらず控除額は減りません。
もし念書を根拠に放棄した人を人数から除外して申告すると、
原則として相続税法第15条第2項に反する誤りとなり、課税上は修正対象となります。
このように、
念書は生前には贈与税のリスク、相続後には相続税の誤りを招くおそれがあり、
法的にも税務的にも「相続放棄」としての効力は一切認められません。
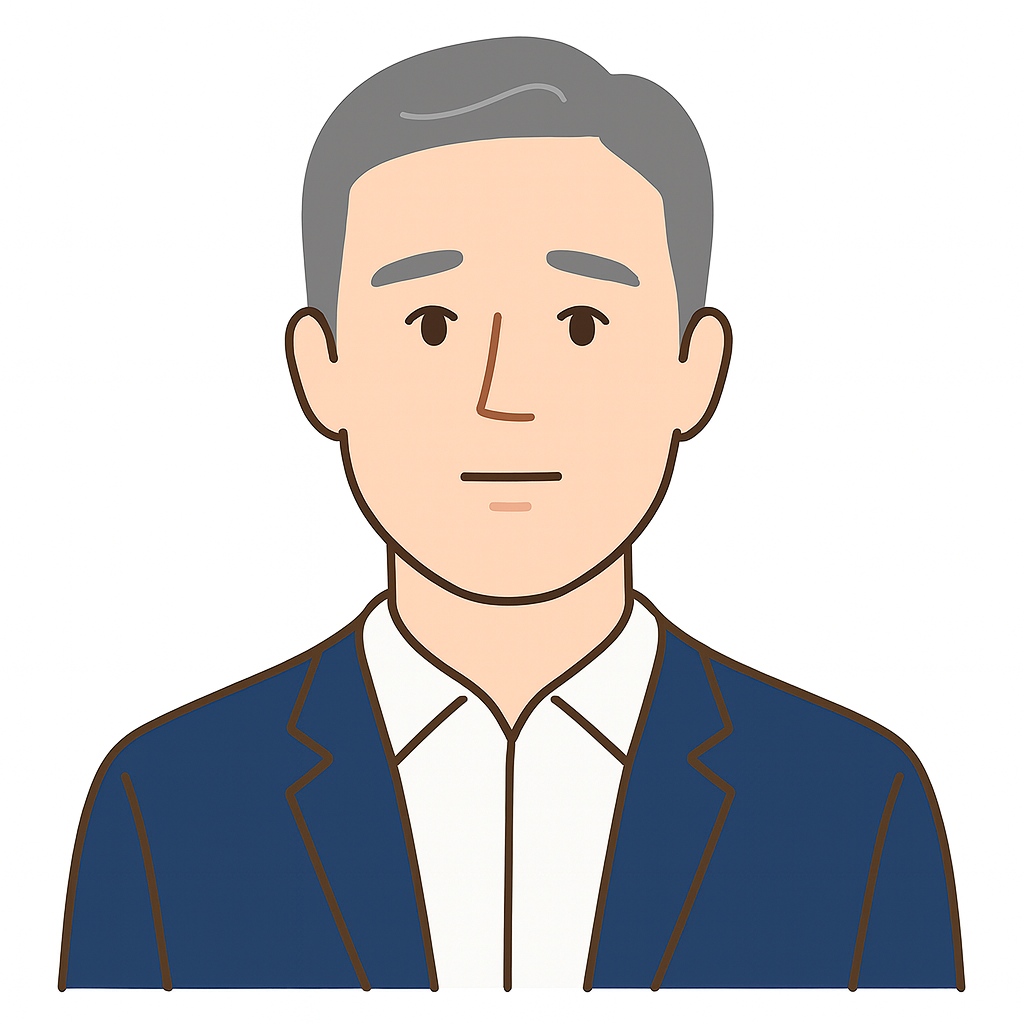
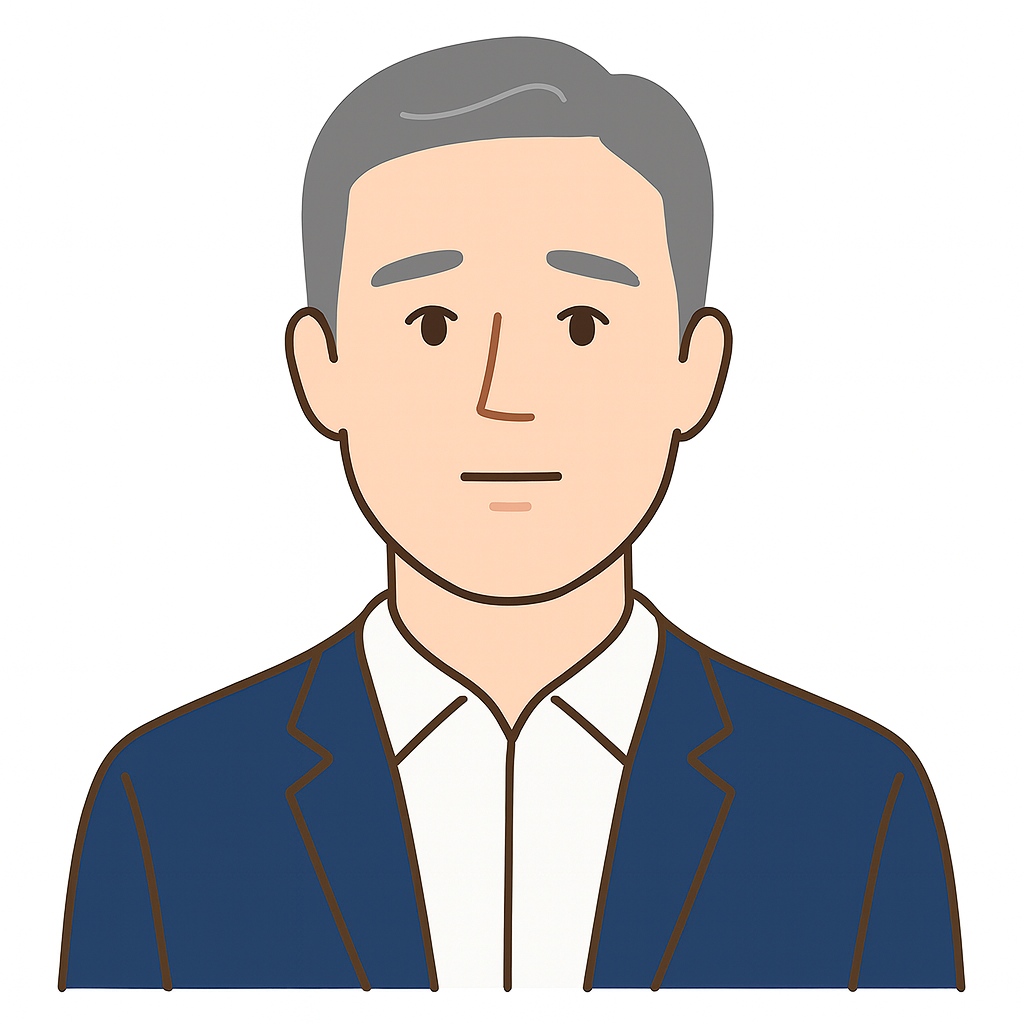
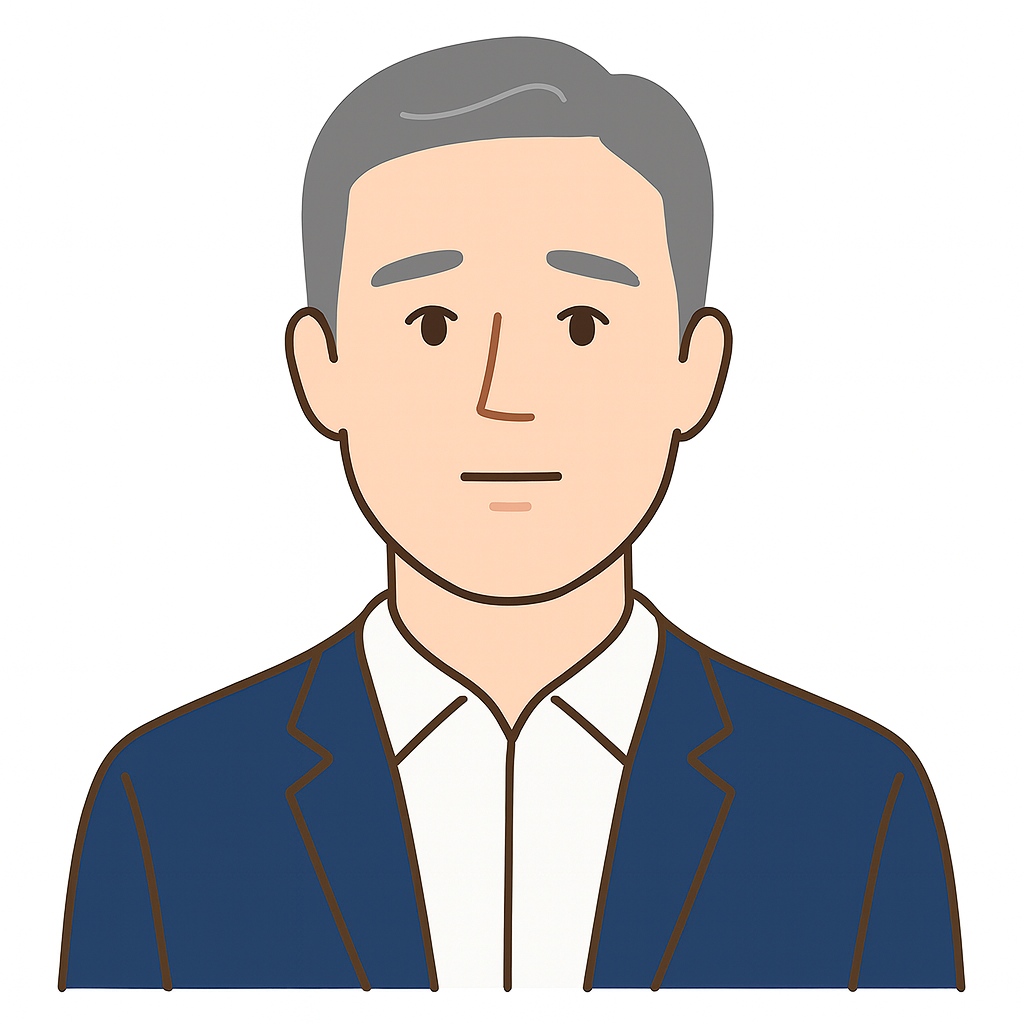
相続しないって念書を書かせて、代わりに現金を渡したんです。



相続しないって念書を書かせて、、代わりに現金や財産を与えていた場合には、原則として贈与税の課税対象となります。
税務では形式よりも実質が重視されるため、念書を条件に財産を与える行為は、
「相続放棄の見返り」という名目であっても生前贈与とみなされます。
放棄の意思があっても、財産を受け取っている以上、それは贈与として課税されるというのが税務署の判断です。
一方、相続が始まった後についても、念書をもって放棄が成立することはありません。
相続税法第15条第2項では、相続放棄があっても**「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」で基礎控除を計算する**と明記されています。
したがって、念書を根拠に放棄した人を人数から除外して申告すると、
基礎控除の算定が誤りとなり、税務署から修正を求められる可能性があります。
生前に財産を渡しても、相続後に放棄を主張しても、
税務上はどちらも「放棄があった」とは扱われず、
贈与税の課税リスクと、相続税の申告誤りの両方を招く点に注意が必要です。
法的に有効な「相続させない」ための方法
「念書では法的にも税務的にも意味がない」ということが分かりました。
では、親として「特定の子には財産を渡したくない」と考えた場合、どんな方法が現実的なのでしょうか。
生前にできる手続の中には、家庭裁判所の関与が必要なものと、遺言書の作成など自分で進められるものがあります。
それぞれの制度の特徴と違いを整理してみましょう。
📘図解:「特定の相続人に財産を渡さない」ための手続
| 手続 | 家庭裁判所の関与 | 効力 |
|---|---|---|
| 念書による相続放棄(生前) | × 関与なし | 無効 |
| 推定相続人の廃除(民法892) | ○ 審判が必要 | 有効(例外的) |
| 遺留分の放棄(民法1049) | ○ 許可が必要 | 有効(要審査) |
| 遺言書による配分調整 | ○ 法的に有効 | 有効(ただし遺留分の制約あり) |
家庭裁判所が関与しない念書は、あくまで家族内の約束にすぎません。
法的拘束力を持つのは、家庭裁判所の手続きを経た場合のみです。
推定相続人の廃除 ― 相続権を失わせる制度
「特定の子に相続させたくない」という気持ちは、相談の現場でもよく聞きます。
この場合、相続放棄の念書ではなく、推定相続人の廃除(民法第892条)という制度があります。
廃除が認められると、その子は相続人の地位を完全に失い、一切の相続権を失います。
ただし、家庭裁判所の審判が必要であり、認められるのは極めて例外的です。
日常的な不仲や、介護をしてくれなかったといった事情では認められません。
虐待、重大な侮辱、犯罪行為など、深刻な非行がある場合に限られます。
遺言によって廃除を指定することも可能です(民法第893条)。
💡税務の視点:廃除が認められない限り課税上は相続人
家庭裁判所が廃除を認めない限り、税務上ではその人も相続人として扱われます。
相続税の計算では、相続開始時点で廃除が確定していない場合、
たとえ廃除の申立て中であっても法定相続人の人数に含めて基礎控除を算出します。
これは、審判が確定するまでは法的に相続人の地位が残るとされているためです。
一方、相続開始時に廃除がすでに確定している場合には、
その人は最初から相続人ではないとみなされ、
相続税法第15条第2項の規定に基づき、基礎控除の人数から除外して計算します。
廃除審判の確定時期と申告期限にも注意が必要です。
相続税法上、法定相続人の数は相続開始時点の状況で確定するため、
廃除の審判が申告期限前に確定した場合は人数から除外して申告できますが、
申告期限後に確定した場合でも、原則として再申告は行いません。
相続開始時にはまだ相続人であったとみなされるため、
その時点の人数で申告した内容は法令上適正とされます。
このように、廃除の確定時期によって税務上の扱いは変わります。
廃除は、家庭裁判所の審判が相続開始時点で確定している場合に限り、その人を法定相続人の数から除外できます。
しかし、審判が確定していない段階では、申立て中であっても相続人として人数に含めて計算します。
遺留分の放棄 ― 現実的だがハードルが高い手続
廃除ほど極端でない方法として、遺留分の放棄(民法第1049条)という制度があります。
推定相続人が家庭裁判所に申し立て、許可を得ることで有効になります。
ただし、許可を得るには以下のような条件を満たす必要があります。
- 放棄が本人の自由意思で行われていること
- 放棄の理由に合理性・必要性があること
- 放棄の代わりに補償(贈与など)を受けていること
これらの要件を満たすのは簡単ではありません。
家族の一方的な判断で手続を進めることはできず、放棄する本人の申立てが必要です。
💬税務の視点:放棄の代償が贈与税の対象になることも
遺留分を放棄する代わりに金銭や財産を渡した場合、その補償分は贈与税の課税対象になることがあります。
家庭裁判所の許可を得た正式な遺留分放棄であっても、
放棄の代償として財産を与えれば、それは“生前贈与”とみなされるためです。
最も現実的な対策:遺言書で取り分を調整する
特定の子に財産を渡したくない場合、最も現実的で法的にも確実なのが、遺言書で取り分を調整する方法です。
遺言書で、該当の相続人には遺留分(最低限の取り分)にあたる財産のみを相続させると定めておけば、
それ以上を請求されることはありません。
親から子への相続では、法定相続分と遺留分の差はおよそ2倍です。
遺言書を作るだけで、渡す財産を半分程度に抑えられるケースもあります。
法律的にも税務的にも、遺言書は最も安全で柔軟な手段です。
💡税務の視点:遺言書と税額シミュレーションをセットで
遺言書は感情的な整理だけでなく、税金の設計にも直結します。
配分次第で相続税の総額が変わるため、遺言を作る際には税額シミュレーションが欠かせません。
遺言書によって「争いを防ぐ」と同時に、「税額を最適化する」ことができます。
法務と税務の両面を踏まえた遺言こそ、最も現実的な相続対策といえるでしょう。
まとめ:念書では意図した相続は実現できない
いまの日本では、家族のかたちや人間関係が多様化し、
「あの子には財産を渡したくない」「関わりたくない」という相談が増えています。
しかし、相続の仕組みは今もなお**“家族全体の公平”を前提**に作られており、
個人の感情や事情をそのまま反映させることはできません。
そのため、生前に「相続しません」といった念書を書かせるケースも見られますが、
念書は法律上も税務上も効力を持たず、相続放棄として扱うことはできません。
家庭裁判所が関与する遺留分放棄や推定相続人の廃除という制度もありますが、
いずれも利用のハードルが高く、理由や手続が厳格に審査されます。
こうした限界の中で、唯一、自分の意思を優先させることができる例外的な仕組みが遺言書です。
相続制度は原則として“家族全体の公平”を守るよう設計されていますが、
遺言書によってはじめて、本人の意思を法的に上位に置くことが認められます。
遺言書を通じて自分の考えを明確にし、税務上の整合性を保つことで、
家族間のトラブルや不要な課税を未然に防ぐことができます。
専門家の助言を得て、法的にも税務的にも筋の通った形で意思を残すことが、
「望まない相続」を避けるための最も現実的な方法です。
税務的にもと言いましたが、実際には、遺言書の作成に税理士が関与していないケースは少なくありません。
その場合、遺言内容が法的には有効でも、税務上の整合性や節税効果が欠けるおそれがあります。
相続税や贈与税の仕組みを前提にした設計を行うことが、
結果的に「争わない・損をしない相続」につながります。
弊所では、遺言書の段階から税務の観点を取り入れ、
将来の申告や納税の負担までを見据えたサポートを行っています。
法律・税務の両面から検討することで、
ご本人の意思と税務上の合理性を両立させた“実務に強い遺言書”を作成することが可能です。
参考・出典情報(2025年10月時点)
- 民法第915条、第938条/家事事件手続法第201条
- 相続税法第15条(2025/3/31改正:政令第123号、財務省令第21号)
- 国税庁『タックスアンサー No.4152』/『令和7年分 相続税の申告のしかた』
- 最高裁『司法統計年報(家事編)令和4年』遺留分放棄の許可件数
- 財務省『令和7年度税制改正 法令・通達等』
- 国税庁税務大学校『税務大学校論叢』第92号
