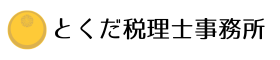面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
障害のある子に安心して財産を残す方法|特定贈与信託で贈与税が非課税に

自分が亡くなったあと、この子の生活は大丈夫だろうか?
障害のあるお子さんやきょうだいを支えるご家族なら、一度は頭をよぎる不安だと思います。
相続や贈与で財産を渡すとき、どうしても重くのしかかるのが税金です。ですが、特定贈与信託という制度を使うと、贈与税の負担をぐっと軽くして、しかも専門機関に財産管理を任せられる仕組みがあります。
この記事では、制度の内容・手続き・注意点・他の制度との違いまで、やさしい言葉で整理してご紹介します。
特定贈与信託とは?
特定贈与信託とは、障害のある方に財産を安心して残すための特別な仕組みです。
親や祖父母が自分の財産を信託銀行に預ける契約を結び、その財産を銀行が管理・運用します。
そして、障害のある方(受益者)は、その信託から定期的に給付を受け取ることができます。
つまり「一度にお金を全部渡す」のではなく、少しずつ、生活を支える形で渡していける仕組みで。

一度に渡してしまうと心配だから、少しずつ管理してもらえるのは安心です。



そうなんです。まさにその安心を制度として形にしたのが特定贈与信託です。
贈与税がかからない金額
ふつうの贈与だと、年間110万円を超えると贈与税がかかります。
ところが、特定贈与信託を使うと非課税枠が大きく広がります。
- 特別障害者:6,000万円まで非課税
(特別障害者=身体障害者手帳1・2級、知的障害の重度判定、精神障害1級など、重度の障害を有する方) - 特定障害者:3,000万円まで非課税
(特定障害者=特別障害者に該当しないが、一定の障害者控除の対象となる方)
たとえば、500万円を一括で贈与したら通常は課税対象ですが、この制度を使えば非課税の範囲内です。



普通に贈与したら税金がかかるのに、信託にするとこんなに非課税になるんですね。



はい、障害のある方を支えるために特別に広い非課税枠が用意されているのです。
特定贈与信託で非課税を受けるための手続き
特定贈与信託は「契約して終わり」ではありません。
信託契約+税務署への事前申告がワンセットになって、はじめて「贈与税が非課税」と認められます。
特定贈与信託の第一歩は、委託者(親や祖父母など財産を持つ人)と、受託者(信託銀行)が契約を結ぶことです。
この契約で「どんな財産を、どんな方法で、誰に給付していくのか」をきちんと決めることで、将来の安心が確保されます。
契約内容には、次のような重要な取り決めが盛り込まれます。
- 信託財産の内容
例:現金、預貯金、有価証券などをいくら信託に組み入れるか - 受益者への給付方法
例:毎月10万円を生活費として給付する/必要なときに医療費を優先的に支払う など - 契約終了時の残余財産の帰属先
例:受益者が亡くなった後、残った財産を他の兄弟姉妹に分ける、あるいは特定の団体へ寄付する 等
👉 ここでの決定がその後の運用に直結するため、信託銀行の担当者や税理士とよく相談して内容を詰めていくことが大切です。
税務署に非課税の適用を申告するためには、信託の内容や受益者の状況を裏付ける書類をそろえる必要があります。「信託の契約が本当に有効か」「受益者が制度の対象となる障害のある方か」を確認するためです。
- 信託契約書の写し
→ 信託銀行が契約時に作成。提出用にコピーを渡してもらえます。 - 障害者手帳などの証明書
→ ご家族が市区町村窓口で取得。銀行や税理士では代行できません。 - 住民票(受益者のもの)
→ これもご家族が役所で取得します。 - 受益権の価格計算明細書
→ 信託財産の価額を計算したもの。通常は信託銀行が作成してくれますが、税理士がチェックすることで安心感が増します。 - 障害者非課税信託申告書(国税庁の様式)
→ 信託銀行がフォーマットを用意し、委託者(親や祖父母など)が署名・捺印したうえで、銀行を経由して税務署に提出します。実務では銀行が作成をサポートしてくれるため安心ですが、非課税要件の確認や財産評価については税理士に相談すると確実です。
信託契約を結んだだけでは、まだ非課税は適用されません。
「障害者非課税信託申告書」を税務署に提出してはじめて、非課税の扱いが認められるのです。
- 提出期限は 「信託契約をした日まで」。
- この期限を過ぎると、非課税の適用は受けられず、通常どおり贈与税が課税されてしまいます。
- 提出するのは委託者(親や祖父母など)。ただし実務的には、銀行や税理士が書式準備や提出サポートをしてくれる場合が多いです。
👉 つまり、「契約して安心」ではなく、税務署への提出がワンセットと覚えておくことが大切です。
一度申告して終わりではなく、契約内容を変えたり、信託財産を追加した場合には改めて税務署へ申告が必要になります。
例えば:
- 毎月の給付額を変更した
- 追加で預金や有価証券を信託に組み入れた
- 契約終了時の残余財産の帰属先を変更した
こうした変更があると「非課税枠を超えないか」「条件に合致しているか」を税務署が再確認するためです。
👉 変更や追加をしたのに申告を忘れると、その分が非課税として認められず課税対象になるリスクがあります。
銀行や税理士に相談しながら、必ず再申告の手続きを行いましょう。
税務署の確認を経て、信託銀行から契約通りに給付が始まります。
- 給付は「毎月10万円ずつ」など契約で定めた金額・方法で行われます。
- 医療費や生活費など、日常生活に必要なお金として受益者が受け取ることができます。
- この給付金は、贈与税も所得税もかからず非課税として扱われます。
👉 一度に大金を受け取るのではなく、定期的に給付されるため、生活を安定的に支えられるのが大きな安心材料です。
補足:通算枠について
- 非課税枠(6,000万円/3,000万円)は受益者一人あたり一生涯の通算枠です。
- 追加契約や変更をして枠を超えた分は、通常の贈与税課税対象になります。
🟢特定贈与信託のメリット
特定贈与信託には、一般の贈与にはない特別な利点があります。
「税金面の優遇」と「安心できる財産管理」の両方を兼ね備えているため、障害のある方とそのご家族にとって強い味方となります。
- 贈与税を大きく節約できる
通常の贈与なら課税されるような多額の財産でも、非課税枠を活用すれば税負担を大きく減らすことができます。 - 信託銀行に管理を任せられる安心感
受益者本人や家族が直接お金を管理しなくても、専門機関が契約に基づいて安全に運用・給付してくれます。 - 定期的に少しずつ給付されるため浪費の心配が少ない
一度に大金を渡さない仕組みのため、生活費や医療費に計画的に使えるようになります。 - 残った財産の行き先をあらかじめ決められる
受益者が亡くなった場合に備えて、残余財産を兄弟姉妹に残す、あるいは福祉団体に寄付するなど、将来まで見据えた取り決めが可能です。
👉 「税金の負担を減らしつつ、生活を安定的に支える仕組みを作れる」のが特定贈与信託の大きな魅力です。家族が安心して将来を託せる、心強い制度といえるでしょう。
特定贈与信託の注意点・リスク
特定贈与信託は大きなメリットがある一方で、気を付けておかないと「思わぬ負担」や「想定外の不利益」につながる可能性もあります。制度を正しく理解し、注意すべき点をあらかじめ押さえておきましょう。
⚠️信託手数料がかかる
- 初期費用:信託財産の1〜2%程度
例:3,000万円 → 30万〜60万円前後 - 管理費用:信託財産の0.2〜0.5%/年
例:3,000万円 → 年6万〜15万円前後 - その他:振込手数料、終了時の残余処理費用など



贈与税がゼロでも手数料はかかるんですね。



そうです。ただし税金に比べればずっと軽い負担です。
⚠️その他のリスク
- 運用次第で元本が減る可能性がある
信託財産の運用方針によっては、景気変動や投資リスクの影響を受け、信託元本が減少する場合があります。 - 契約によっては途中解約ができない
一度信託に入れると、原則として中途解約できない場合が多いため、柔軟性が制限されます。 - 銀行によっては成年後見人が必要になる場合がある
契約や管理にあたり、受益者の保護の観点から「成年後見制度の利用」を求められるケースもあります。
贈与税と信託手数料の比較イメージ
| ケース | 贈与の方法 | 税金・費用の目安 |
|---|---|---|
| Aさん(特別障害者の子に3,000万円贈与) | 通常の贈与 | 贈与税:約1,200万円 |
| Bさん(同じ条件) | 特定贈与信託を利用 | 贈与税:0円/初期費用30〜60万円/管理費6〜15万円/年 |



同じ3,000万円でも、税金で1,200万円かかるのと、手数料だけで済むのでは全然違いますね。



はい。数字で比べると、この制度のメリットがよく分かりますね。
他の制度とどう違うの?
障害のある方を支える制度は特定贈与信託だけではありません。
代表的なのが「障害者扶養共済制度」です。こちらは信託とは違い、親が掛金を払い続けることで、親の死後に子へ終身年金が支給される仕組みです。
障害者扶養共済制度の特徴
- 加入できるのは65歳未満の親
- 掛金は年齢ごとに一定額(例:30歳で月額9,000円前後)
- 親が亡くなった後、子に月額2万円(2口で4万円)を一生涯支給
- 年金は非課税
つまり「毎月の掛金は小さくても、親が亡くなったあと子どもが一生涯にわたって年金を受け取れる」という仕組みです。



扶養共済は少額でも一生もらえるのが安心ですね。



はい。ただしまとまった資金を残すには特定贈与信託の方が向いています。
👉 特定贈与信託は“終身給付”ではありません。契約で定めた信託財産が尽きれば給付は終了します。
そのため「長く安心を保障する終身年金型」の扶養共済と、「まとまった資金を計画的に残す信託型」の特定贈与信託は、役割が補完関係にあると言えます。
特定贈与信託と障害者扶養共済の違い
| 項目 | 特定贈与信託 | 障害者扶養共済制度 |
|---|---|---|
| 財源 | 親や祖父母の財産 | 親が掛金を払い続ける |
| 支給 | 信託銀行から定期的に給付 | 親の死後に月額年金 |
| 税制 | 贈与税が非課税(上限3,000万/6,000万) | 年金が非課税 |
| メリット | 多額を非課税で残せる/管理も安心 | 掛金が安い/終身給付 |
| デメリット | 手数料や運用リスク | 一括資金を残せない/加入年齢制限 |
まとめ
特定贈与信託は、
- 贈与税を気にせず大きな財産を渡せる
- プロに管理を任せられる
- 障害のある子や家族の生活を長期的に守れる
という心強い制度です。
👉 ご家庭によっては、「障害者扶養共済」と組み合わせることで、まとまった資金の安心+終身年金の安定という二重の備えをつくることも可能です。



うちの場合は、どちらの制度も良さがあるので、どう組み合わせるかを考えたいです。



はい、ご家族の状況に合わせてプランを立てれば、将来に向けて安心できる備えができますよ。
今後は制度の見直しや活用促進の動きも進むでしょう。金融機関のサービスが拡充されれば、より利用しやすくなる可能性もあります。
そして、制度を適切に活用するには専門的な知識が欠かせません。
税理士がサポートすることで、
- 適用条件を確実にクリアできる
- 手数料や税金の比較を冷静に判断できる
- 将来の相続全体を見据えたプランを立てられる
といった大きなメリットがあります。
安心して未来を託せる制度のひとつとして、ぜひ税理士と一緒に最適な方法を考えてみてください。
📝 補足:特定贈与信託の委託者になれる人
本文では「親や祖父母が委託者」として説明しましたが、法律上は第三者でも特定贈与信託を設定することが可能です。
例えば、叔父や叔母、兄弟姉妹、さらには親族以外の方が、障害のある方を受益者として財産を信託することも制度上は認められています。
ただし、実務では「親族からの贈与」を前提とすることが多く、第三者が委託者となる場合は信託銀行での審査が慎重になる傾向があります。
👉 制度の柔軟性として知っておくと安心ですが、実際に検討するときは必ず銀行や税理士に相談することをおすすめします。