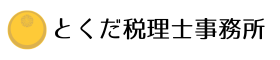面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
【不動産売却】健康保険料や国民健康保険料はどうなる?影響と対策を税理士が解説


自宅を売ったら健康保険料がすごく上がったって聞いたんですが…



親から相続した不動産を売ったら、国民健康保険料が高くなるらしいんです…
不動産を売却された方から、こうしたご相談をよくいただきます。
“税金は覚悟していたけど、健康保険料まで上がるの?”と驚かれる方が少なくありません。
実際には、加入している保険の種類によって「全く影響しない人」もいれば「数十万円単位で保険料が増える人」もいます。
この記事では、税理士の立場から 「どんな人が影響を受けるのか」「保険料アップを防ぐ方法はあるのか」 を、わかりやすく整理してお伝えします。
まず結論から
- 協会けんぽ・健康保険組合・共済など「給与型の保険」加入者
これらの制度は、毎月の給与や賞与の金額を基準に保険料を計算します。会社員や公務員が加入する仕組みで、給与以外の所得(たとえば不動産売却益や株式の譲渡益など)は計算に含まれません。したがって、不動産を売却して大きな利益が出ても保険料に影響はありません。 - 国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者
こちらは前年のすべての所得(給与所得、事業所得、年金、譲渡所得など)を合算して保険料を計算します。自営業の方や退職して無職の方、年金生活の方などが多く加入している制度です。不動産を売却して利益が出れば「前年所得」に反映されるため、保険料の「所得割」が増え、結果として数十万円単位で負担が上がる可能性があります。
つまり、「国保・後期高齢者医療制度かどうか」が分かれ道になります。
給与以外の所得を保険料計算に含めるかどうか が制度の大きな違いであり、ここが「国保・後期高齢者医療制度かどうか」が分かれ道になる理由です。
不動産売却と「利益」の考え方
不動産を売ったときに得られる利益を、税務上は「譲渡所得(じょうとしょとく)」と呼びます。
ここでいう「利益」とは、売却価格そのものではなく、買ったときの金額や手続きにかかった費用などを差し引いた“純粋なもうけ”のことです。
具体的には、次のように計算します。
計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(購入価格 + 諸費用)- 特別控除
売却価格:実際に売れた金額
購入価格(取得費):買ったときの金額(建物の場合は減価償却後の金額を使います)
諸費用(譲渡費用):仲介手数料、登記費用、測量費、建物の取り壊し費用など
特別控除:自宅の売却なら最大3,000万円、相続空き家なら3,000万円、など条件付きで利益から差し引ける制度
たとえば、3,500万円でマンションを売っても、購入時に2,000万円かかり、手数料や登記費用が200万円、さらに「3,000万円特別控除」が使えれば、最終的な譲渡所得はゼロ、つまり課税対象の利益は残らないことになります。
健康保険制度ごとに違う扱い(比較表)
| 保険制度 | 主な加入者 | 保険料の算定基準 | 不動産売却益の影響 |
|---|---|---|---|
| 協会けんぽ | 中小企業の会社員 | 給与・賞与額 | 影響なし |
| 健康保険組合 | 大企業の会社員 | 給与・賞与額 | 影響なし |
| 共済組合 | 公務員 | 給与・賞与額 | 影響なし |
| 国民健康保険 | 自営業者・無職 | 前年所得(住民税ベース) | 影響あり |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 | 前年所得(住民税ベース) | 影響あり |
給与を基準にする健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合など)は、会社から支払われる給与や賞与の金額だけをもとに保険料を計算します。そのため、株式の売却益や不動産の売却益といった「給与以外の所得」は一切カウントされません。つまり、不動産をいくらで売っても保険料は変わらない仕組みです。
一方で、国民健康保険や後期高齢者医療制度は、前年のすべての所得(給与所得、事業所得、年金所得、譲渡所得など)を合算して住民税の課税所得をベースに保険料を計算します。したがって、不動産の売却益(譲渡所得)も計算に組み込まれるため、利益が大きいと「所得割」の部分が跳ね上がり、結果的に保険料が大きく増えるのです。
国保の仕組みと保険料の増え方
国民健康保険の保険料は、いくつかの要素を組み合わせて計算されます。代表的なのは次の3つです。
- 所得割:前年の所得金額に応じて課される部分です。会社員の給与、年金、自営業の事業所得、不動産の売却益(譲渡所得)など、課税対象となる所得が多ければ多いほど、この部分が大きくなります。
- 均等割:加入している人数に応じて一律にかかる部分です。世帯に2人加入していれば2人分、3人なら3人分とカウントされます。
- 平等割:世帯ごとに定額でかかる部分です。世帯人数に関係なく「世帯単位で1つ」かかります。
このうち、不動産売却によって増えるのは 所得割 です。譲渡所得が大きくなると、その年の所得総額が一気に増えるため、所得割が跳ね上がります。
さらに国保の特徴として、
- 前年の所得で翌年度の保険料が決まる ため、売却した翌年に保険料が急増するケースが多いです。
- 自治体ごとに税率や上限額が異なるため、「同じ2,000万円の利益」でもA市では上限いっぱい、B市ではまだ余裕がある、という差が出ます。
たとえば、ある市では所得割の税率が10%で上限額109万円、別の市では12%で上限額100万円というように差があるため、「どこに住んでいるか」で保険料の増加額が変わる点も重要です。
計算例(シミュレーション)
仮に、ある自治体で国保に加入している世帯のケースを見てみましょう。
| 譲渡所得(売却益) | 年間保険料の増加目安 |
|---|---|
| 500万円 | 約20万円前後増加 |
| 1,000万円 | 約40万円前後増加 |
| 2,000万円 | 上限に達し50万円超増加も |
| 3,000万円 | 上限(2025年度109万円)に到達 |
※この表はあくまで概算のモデル例です。国民健康保険料は自治体ごとに保険料率が異なるため、実際の金額は大きく変わることがあります。



500万円の利益で20万円も保険料が増えるんですね、大変…
知っておきたい特別控除のルール
保険料が増加するのを防ぐためにも、譲渡所得を小さくできる「特別控除」は非常に重要です。代表的な制度を紹介します。
- 3,000万円特別控除(居住用財産の特例)
自宅を売却したときに使える制度で、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。
適用条件は、実際に居住していた家であることや、一定期間内に売却することなど。例えば、3,500万円で家を売り、購入費や経費を差し引いて利益が2,500万円残った場合でも、この特例を使えば課税上の利益はゼロになります。結果的に、税金だけでなく国保の保険料アップも避けられるのです。 - 空き家特例控除(3,000万円控除)
相続で取得した家屋を売却する場合に使える制度です。亡くなった親が住んでいた住宅で、耐震リフォーム後に売却するか、取り壊して土地を売却するなど一定の条件を満たせば、こちらも3,000万円まで控除できます。相続不動産を売ったときに「思った以上に利益が出て保険料が跳ね上がる」ケースがあるため、この特例の有無は非常に大きな差になります。 - 10年超所有の軽減税率特例
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合に適用されます。通常より低い税率(所得税14.21%・住民税9% → 合計23.21%)が適用されるため、直接的には税率が下がる特例ですが、譲渡所得の算定にも影響します。結果として課税額が減ることで、税負担と合わせて「保険料に反映される利益部分」も軽くできる場合があります。
見落としがちなケース
不動産売却による健康保険料の影響は、単に「売却で利益が出たかどうか」だけで決まるものではありません。加入している健康保険の種類や、家族の扶養関係、年金収入の有無などによっても結果が大きく変わります。
実際には、多くの方がこうした背景要因を見落としがちで、「まさか扶養から外れて自分で国民健康保険料を払うことになるとは思わなかった」「年金だけなら安心だと思っていたのに、売却で一気に保険料が上がった」と驚かれるケースが少なくありません。
だからこそ、売却前に自分や家族の加入状況を整理し、想定外の負担が出るリスクを把握しておくことが大切です。
扶養から外れるリスク
専業主婦や学生、定年退職後に子どもの扶養に入っている方などが、不動産売却で大きな利益を得ると、その年の所得が扶養の基準を超えてしまう可能性があります。扶養から外れると、自分自身で国民健康保険に加入しなければならず、その年だけ数十万円単位の保険料を支払うことになるケースもあります。「売却益は臨時収入のはずが、予想外の出費が増えた」と感じる典型例です。
ただし、扶養から外れるかどうかの判断は、加入している健康保険制度によって異なります。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合
原則は「年間収入130万円(60歳以上や障害者は180万円)を超えると扶養に入れない」とされています。ただし、一時的な土地の売却益のように「継続性がない収入」は除外される場合があり、最終判断は支部ごとの運用に委ねられます。
健康保険組合の場合
組合ごとに「被扶養者認定基準」を設けており、譲渡所得を厳格にカウントするところもあれば、一時的収入は扶養判定に含めないところもあります。そのため、同じ状況でも組合によって結論が違うことがあります。
年金生活者+不動産売却
普段は年金収入だけで、国民健康保険料もそれほど高額にはならない高齢者世帯。しかし、自宅や土地を売却して数千万円の利益が出ると、翌年度の保険料が一気に上限に近づきます。「年金しかないから安心だと思っていたのに、売却のせいで保険料が跳ね上がった」と驚かれることが多いケースです。
相続した不動産の売却
親から相続した空き家や土地を売却するときも注意が必要です。長年放置していた土地でも思いがけない高値がつき、譲渡所得が大きくなることがあります。
「空き家の3,000万円特例があるから大丈夫」と思っていたのに、耐震リフォームをしていなかった、相続後3年以内に売却しなかった、被相続人が一人暮らしではなかったなどの理由で条件を満たさず、結局特例が使えなかったというケースも実際にあります。
その場合、控除が効かないため譲渡所得がそのまま課税対象となり、翌年度の国民健康保険料も大幅に増加してしまいます。制度の適用条件を細かく確認せずに売却してしまうと「思わぬ保険料アップ」という結果になりかねません。
保険料アップを抑える工夫
不動産を売却しても、工夫次第で譲渡所得を抑え、結果として健康保険料の増加を防げる場合があります。代表的なポイントは次の3つです。
- 特別控除を忘れず適用
居住用財産を売却したときの「3,000万円特別控除」や、相続した空き家を売却したときに使える「空き家の3,000万円特例」などは非常に強力です。これらを適用できれば譲渡所得がゼロになるケースも多く、その場合は税金も保険料も増えません。ただし、居住していた期間や売却時期など細かい条件があるため、売却前に必ず確認することが大切です。 - 取得費・譲渡費用を漏れなく計上
「購入価格(取得費)」や「売却時の経費(譲渡費用)」は、譲渡所得から差し引けます。仲介手数料、登記費用、測量費、建物の取り壊し費用、場合によってはリフォーム代なども対象です。これらを正しく計上すれば、課税される利益を数百万円単位で減らせることもあります。逆に領収書や契約書を紛失して証明できないと、認められないことがあるので注意が必要です。 - 売却のタイミング調整
国保の保険料は「前年の所得」で決まるため、売却する年を工夫するだけでも負担が変わります。たとえば、退職後で給与所得が少ない年に売却すれば、合計所得が抑えられて保険料も軽くなります。逆に、他の大きな所得(退職金や事業売却益など)が出る年と重なると、一気に保険料が跳ね上がるので注意が必要です。
まとめ
ここまで、不動産売却と健康保険料の関係について解説してきました。最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。
- 会社員や公務員など給与型の健康保険加入者
協会けんぽ・健康保険組合・共済などに加入している方は、保険料の基準が給与や賞与だけなので、不動産を売却しても保険料には一切影響しません。 - 国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者
自営業者、無職の方、年金生活者が多く加入する制度では、譲渡所得も所得に含まれるため、売却益があると保険料が大きく上がる可能性があります。場合によっては数十万円単位で増えることもあります。 - 特別控除や経費の計上で利益を抑えられる
居住用財産の3,000万円特別控除や空き家特例、仲介手数料・登記費用などの譲渡費用を正しく申告すれば、課税対象となる利益を大幅に減らせます。結果的に、税金だけでなく保険料の増加も抑えられます。 - 扶養に入っている人は注意
専業主婦や学生、定年退職後の親などが扶養に入っている場合、不動産売却で大きな利益が出ると扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければならなくなることがあります。その結果、予想外の保険料負担が発生するリスクがあります。 - 上限額は年々引き上げられている
国民健康保険料の上限は、2024年度106万円、2025年度109万円と上昇しており、今後も医療費増大に伴ってさらに変動する可能性があります。「自分は上限まではいかないだろう」と油断せず、常に最新の制度を確認することが大切です。
不動産の売却は、一度に数百万円から数千万円規模の利益や損失が動く大きな取引です。その影響は税金だけでなく、加入している健康保険の種類によっては保険料にも及びます。
不動産の売却を検討している方は、事前に税理士に相談し、譲渡所得と保険料の検討を行うことを強くおすすめします。そうすることで、“こんなはずではなかった”という事態を避けられます。