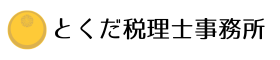面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
樹木希林 ― 不動産と想いを整理した“終活の完成形”

有名人の遺言書シリーズ — 遺す人、遺さない人、税理士が読み解く10の物語
遺言書は「いつか」ではなく「いま」考えるもの。
“その時”が来てからでは、もう本人の意志を確かめることはできません。
けれど、いざ書こうとすると、制度や形式の壁が高く感じられるものです。
そんなときは、有名人たちの遺言をのぞいてみましょう。
そこには、家族への想い、人生のけじめ、そして制度を通して想いを託す知恵が見えてきます。
がんという病は、人によって経過も結末もさまざまです。
けれど、限られた時間をどう生きるかという問いを突きつける病であることは確かでしょう。
樹木希林さんは、その時間を「終わりの準備」ではなく、「生の整理」に使いました。
晩年まで現場に立ち続け、身の回りを整え、そして“自分の生き方を制度の中に仕舞っていく”ように。
一部報道では、公正証書遺言を作成していたとも伝えられています。
公式な確認はありませんが、もしそれが事実なら──病の進行とともに意思を確かに残す、合理的で静かな選択でした。
希林さんの終活は、感情を秩序で支えようとした行為だったように見えます。
それは理想ではなく、生活者としての現実的な判断だったのかもしれません。
🗂 プロフィールメモ:樹木希林(きき・きりん)
1943年東京生まれ。本名・内田啓子。文学座出身の俳優として、
ドラマ『寺内貫太郎一家』や映画『万引き家族』など、多くの名作に出演。
1973年にロック歌手の内田裕也氏と再婚し、一女・内田也哉子さんをもうける。
夫婦は長く別居状態ながら、法的な婚姻関係を生涯維持した。
2004年に乳がんを公表。転移を明かしながらも活動を続け、
2018年、自宅で死去(享年75)。
生前から葬儀や遺品整理まで自ら準備したと報じられている。
本稿は、公開された報道内容を素材として、
「仮に報じられている状況が成り立つとしたら、法律上どのような仕組みが動くのか」を解説するものです。
個別事情やご家族の意図を推測・断定する目的ではありません。
家族を制度でつなぐということ
夫の内田裕也さんとは、結婚以来ほとんど別居生活でした。
裕也さんが一方的に離婚届を出したこともありましたが、希林さんは無効を主張し、婚姻関係を続けました。
後年のインタビューで「“重し”があることで助かっている」と語っています。
離婚しなかった理由は明言されていません。
けれど結果として、婚姻を継続したことで希林さんは法的な配偶者の地位を保ちました。
税の制度で言えば、彼女の死後に夫が相続人となる際、
相続税の「配偶者の税額軽減」が適用できる関係を維持していたことになります。
感情的なつながりが薄れても、制度の上では家族として残す。
離婚しないという選択は、感情の整理というより、生活の秩序を整える判断に近かったのかもしれません。

婚姻を続けるという“形”が、本人にとっても家族にとっても支えになることがあります。
感情だけで整理しないという選択に、生活者としての知恵を感じます。
不動産の整理と“棚卸しとしての終活”
希林さんは、都内に複数の不動産を所有し、賃貸経営を行っていたと報じられています。
所有件数や財産規模は公表されていませんが、
いずれにせよ「動かしにくい財産」を抱えていたことは確かでしょう。
不動産は、評価・管理・分割の三点で後の世代を悩ませる財産です。
誰が住み続けるのか、誰が管理を担うのか、どの土地を売却して納税に充てるのか。
一度の分割で全てを解決するのは容易ではありません。
もし希林さんが生前に整理を進めていたとすれば、
それは節税というよりも、家族が迷わないように整えるための準備。
税理士の視点から見れば、それは生活と税の両方を調和させる設計であり、
「誰が受け取るか」よりも「誰が無理なく引き継げるか」を考える発想です。



もらうより、“持ち続けること”が難しい財産。それが不動産です。
だからこそ、生前に整理しておく意味が大きいんです。
小規模宅地等の特例を見据えた設計
相続税の世界では、居住用や事業用の土地の評価を下げられる「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を確実に使うには、どの土地を誰が相続するかを早い段階で明確にしておくことが大切です。
複数の不動産を持つ家庭ほど、その設計の違いが税額に大きく影響します。
分割協議に時間がかかると、制度を十分に活かせないこともあります。
適用を確実かつスムーズにするには、
遺言で承継の形を定めておくことがもっとも現実的です。
遺言があるだけで、家族は迷わず動ける。
結果的にそれが、税務上も精神的にも安心をもたらします。



特例は“知っているか”ではなく、“使えるように準備しているか”。
遺言で承継先を決めておくことで、制度ははじめて確実な味方になります。
「誰に何を残すか」より、「誰が困らないか」
一部報道では、主な不動産は娘の家族に引き継がれ、
夫には生活資金となる財産が残されたとも伝えられています(公式資料は未確認)。
もしそうであったなら、それは“人に合わせた財産承継”と言えるでしょう。
不動産は管理や納税の責任を伴う。
それを扱える人に託し、生活のための資産を必要な人に残す。
財産を平等に分けるのではなく、適材適所に分ける。
その考え方は実務的で、現実的な愛情の形でもあります。
希林さんの終活は、節税や効率だけを目的にしたものではなく、
相続後の混乱を避けるために意図を整理しておく行為でもあったのかもしれません。
遺言は、たんに財産を分けるための書類ではなく、
家族の関係を整理しておくための制度でもあります。
そう考えると、彼女の遺言設計は、
生活の現実を制度の中で整理しようとした一つの試みだったといえます。



遺言は、制度の枠を借りて想いを整理する作業。
書類の向こうには、いつもその人の生き方が見えます。
離婚しなかったという終活設計
婚姻を続けたまま人生を終えたことで、希林さんは家族の秩序を制度的に保ちました。
夫の裕也さんは翌年に亡くなります。
結果的に相続税の観点からは、二次相続(夫の相続)が早く訪れたため、
一次相続での税負担軽減効果は大きくなかった可能性があります。
おそらく、彼女が守ろうとしたのは“数字の軽減”よりも“生活の継続”。
婚姻という形式を制度の中に残したことは、
残される人が戸惑わずに生活を続けるための配慮だったと考えられます。
節税の工夫を取り入れながらも、
最終的には“家族が混乱しない構造”を優先した。
それは理想化された美談ではなく、現実を知る人間としての判断だったと思われます。



数字の上では最善でなくても、その人にとっていちばん自然な形を選ぶことがあります。
相続は数字だけでなく、生き方の延長にあるんです。
制度で想いを残す
希林さんの終活は、金額の多寡ではなく、
“どう残すか”という構造にこそ価値がありました。
公正証書遺言による確実性、婚姻継続による法的安定、
そして不動産整理という現実的な終活。
制度を通して、自分の生き方を整える。
それは、感情を否定することではなく、
感情を制度という形に変換して残す作業です。



制度は形を決めるものですが、その形の中に、どんな想いを込めるかは人の側にあります。
遺言もまた、制度を通して想いを整えるための道具なんです。
樹木希林さんのように、病を抱えながらも
ご自身の生き方や家族への想いを整理しようと考えている方へ。
終活や遺言作成は、財産をどう残すかだけでなく、
これからの生活や家族の安心を整える時間でもあります。
弊所では、公正証書遺言の作成サポートをはじめ、
相続税の試算や、将来を見据えた相続税対策まで、
税理士として丁寧にお手伝いしています。
じっくり考えたい方は、どうぞご相談ください。
静かな対話の中で、制度と想いを整えるお手伝いをいたします。
🔎 注意:出典と表現について
本記事は、公開資料・報道・研究文献など、一次確認が可能な範囲に基づき執筆しています。
家族関係や経歴に関しては、百科事典的資料(ウィキペディアほか一般公開情報)を参照しています。
遺言の形式(公正証書遺言であったか)、相続財産の具体的配分、税制上の設計意図などについては、
一次資料や公式発表による確認はできていません。
文中の税務解説(小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など)は、
一般的な制度説明として記載しています。
樹木希林さんの終活に実際に適用されたか、またその意図を示す発言は確認されていません。