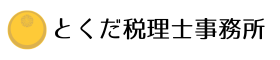面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
リビングニーズ特約と相続税──利用前に知っておきたい税金の注意点
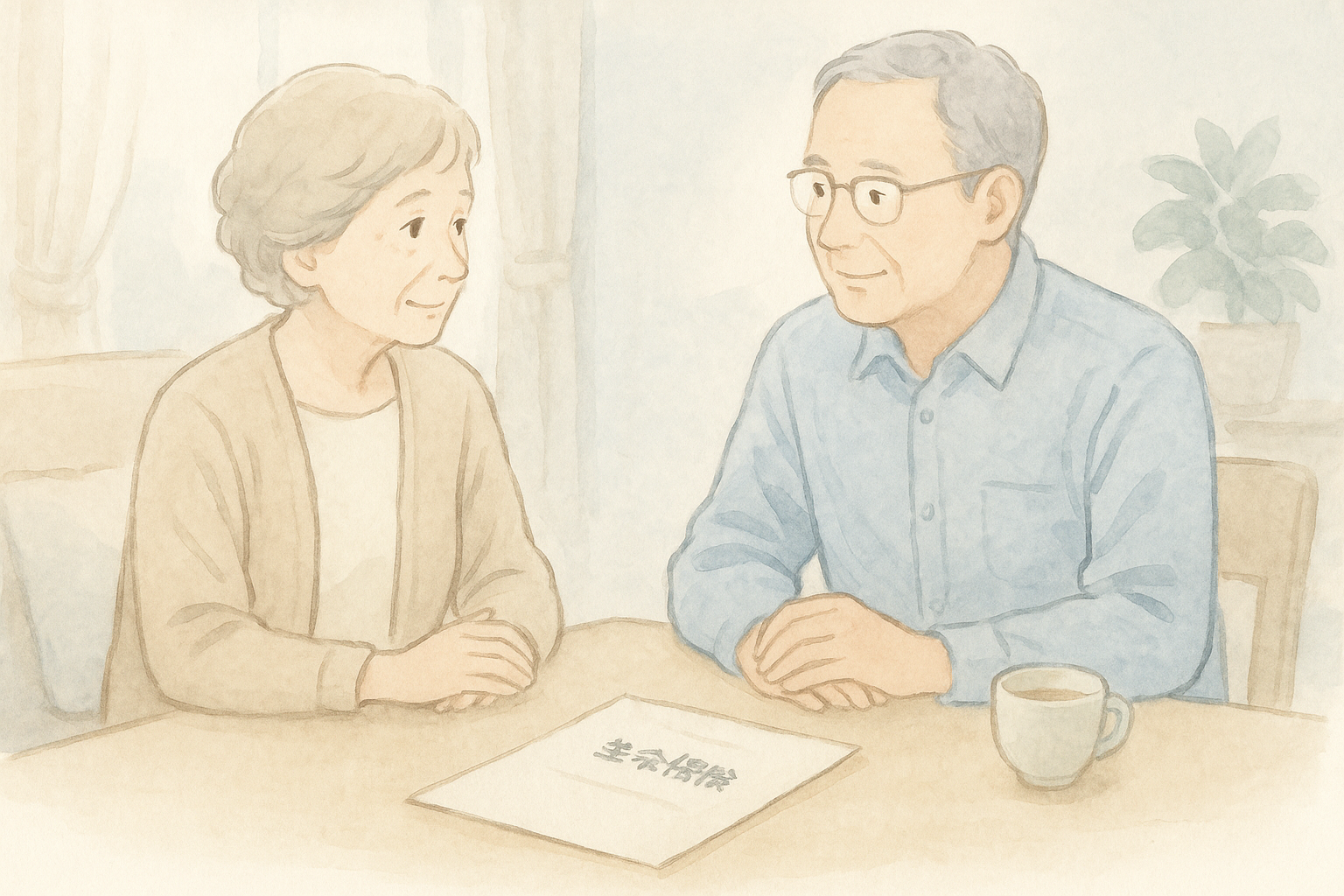
生命保険の「リビングニーズ特約」という制度をご存じでしょうか。
余命6か月以内と診断されたとき、死亡保険金の一部を生前に前払いで受け取れる仕組みです。
医療費や介護費にあてられることも多い制度ですが、
その使い道に制限はなく、本人が自由に使えます。
ただし──
相続税の面では思わぬ注意点があります。
それは、
生前に受け取った分が「死亡保険金」ではなくなるため、
相続税の非課税枠(500万円×法定相続人)の対象から外れるという点です。
リビングニーズ特約のしくみ
リビングニーズ特約は、生命保険契約に付けられる「死亡保険金の前払い制度」。
被保険者が余命6か月以内と診断されたときに申請し、
本人が保険金の一部を受け取ることができます。
- 被保険者=保険金の権利を持つ本人
- 支払時期=生前
- 受取人=本人(原則)
つまり、リビングニーズ特約は本人が自由に使える生前給付です。
旅行に使っても、寄付しても構いません。
代理人が受け取る場合もありますが、それは本人が手続きできないときの例外的な方法です。
生前に受け取っても所得税はかからない
リビングニーズ特約による給付金は、
所得税の課税対象にはなりません。
国税庁は、この給付金を「余命6か月以内と診断された被保険者が、
治療や療養などのために受け取るもの」と位置づけています。
働いて得る収入や投資の利益とは性質が異なり、
本人の生活を支えるための資金として扱われるため、課税されないのです。
そのため、給付金を受け取っても所得税の確定申告は不要です。
ただし、このお金は“死亡保険金の前払い”にあたるため、
相続時に使える死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)には含まれません。
相続税の計算上「非課税枠」を使える金額が減るしくみ
リビングニーズ特約によって支払われる給付金は、被保険者が生前に受け取るため「死亡保険金」ではありません。
そのため、相続税法第12条で定める「生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)」の対象外となります。
給付を受けた分は「死亡保険金の前払い」として扱われるため、
亡くなったときに支払われる死亡保険金の額が減ります。
結果として、相続税の課税価格の計算において非課税限度額を適用できる金額が小さくなるのです。
【具体例】
契約内容:死亡保険金1,000万円
法定相続人:2人(非課税限度額=500万円×2=1,000万円)
| 区分 | 支払時期 | 税目 | 相続税の非課税限度額の扱い |
|---|---|---|---|
| リビングニーズ給付金500万円 | 生前 | 所得税(非課税) | 相続税の非課税限度額の対象外 |
| 残りの死亡保険金500万円 | 死亡後 | 相続税 | 相続税の非課税限度額(上限1,000万円)のうち500万円を適用可能(残り500万円は未使用) |
このように、非課税限度額そのもの(上限1,000万円)は変わりませんが、
適用できる死亡保険金が減るため、非課税限度額をすべて使い切れない結果になります。
もともと相続税の節税を目的に生命保険に加入していた場合でも、
リビングニーズ特約を利用すると、死亡保険金が減ることで相続税の非課税限度額を十分に活用できなくなる可能性があります。
契約金額や法定相続人の人数によっては、結果的に節税効果が薄れることもある点に注意が必要です。

リビングニーズ特約って税金がかからないと聞きました。
だったら使った方が得ですよね?



所得税はかかりませんが、
その分、死亡保険金が減って相続税で非課税枠を使える金額も小さくなります。
もともと相続税の節税を目的に生命保険に入っていた場合は、
リビングニーズ特約を使うことでその効果がなくなってしまうことがあるんです。



えっ、相続税の節税のために入っていた保険なんですが、
特約を使うと意味がなくなるんですか?



そうなんです。
医療費などで確実に使う目的ならいいですが、
“相続税対策”としての保険効果は、リビングニーズを使うと消えてしまいます。
非課税は“残された家族のため”ではなく、“生きている本人のため”に使われることになるわけです。
本人が受け取った給付金の相続上の扱い
被保険者本人がリビングニーズ給付金を受け取り、
そのまま亡くなった場合、使わずに残っていた金額は本人の遺産になります。
給付金を医療費や介護費などに使い切れば相続財産は残りませんが、
残額があれば、それは現金として相続税の課税対象になります。
リビングニーズ給付金1,000万円のうち、700万円を医療費に使用し、
残り300万円を口座に残したまま死亡した場合
→ 残額300万円は相続財産として申告対象。
この残額は「保険金」ではなく「預金」として扱われます。
したがって、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)を適用することはできません。
リビングニーズ給付金のうち、使われずに残った分は、
あくまで通常の相続財産に含まれる──これが整理のポイントです。
代理受領の場合
被保険者本人が請求手続きできない場合には、
保険会社が指定した「代理受領者(配偶者など)」に給付金を支払うことがあります。
これは、あくまで本人の代理として受け取る制度であり、
代理受領者の財産になるわけではありません。
代理受領された給付金のうち、
使わずに残っていれば被相続人本人の遺産として遺産分割の対象になります。
逆に、家計費など本人以外のために使えば、
実質的には贈与とみなされる可能性があります。
税務上の整理は次のとおりです。
| 状況 | 税務上の取扱い | コメント |
|---|---|---|
| 保険会社の明細に「代理受領者:妻」などと明記され、本人の治療費や介護費に使用した場合 | 被相続人本人の財産として扱う(預り金) | 本人のために使用しており、贈与には該当しない。相続開始時に残額があれば被相続人の預金として計上。 |
| 代理受領された給付金が本人名義口座ではなく家族名義口座に入金された場合 | 実質的には本人の預金(名義預金)として扱う | 資金の出所・使途が本人に帰属することを説明できれば問題なし。 |
| 家計費など、本人以外の生活費として使用していた場合 | 家族への贈与とみなされる可能性あり | 贈与税の課税対象となるおそれ。金額・使途・本人の意思確認が重要。 |
代理受領はあくまで「本人の代理行為」であり、
給付金の法的な受取人(経済的所有者)は被保険者本人です。
したがって、代理受領者(配偶者など)の名義に入金されても、
本人の療養費などに使われている限りは本人の財産処分として問題ありません。
ただし、給付金を本人以外のために自由に使った場合、
その支出部分は実質的な贈与(相続税法第3条第1項第1号)とみなされ、
贈与税の課税対象となる可能性があります。
まとめ──リビングニーズ特約を使う前に知っておきたい、相続税への影響
リビングニーズ特約は、本人が余命期間をどう過ごすかを自由に選ぶための制度です。
給付金を受け取っても所得税はかかりませんが、
その分、死亡保険金が減るため、相続税の非課税枠の対象となる金額も小さくなります。
生前に受け取るメリットは「自由に使えること」、
デメリットは「相続で控除できないこと」。
相続税の節税を目的に生命保険に加入している場合は、
リビングニーズ特約を使うことでその効果がなくなる可能性があります。



リビングニーズ特約の給付金は、医療費に使っても、旅行に使っても構いません。
ただし、その分はもう“死亡保険金”ではなくなる。
相続税の非課税枠の対象から外れる点だけは、しっかり理解しておきましょう。