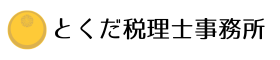面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
相続が続いたとき⑤:相次相続控除──短期間に続く相続の税負担を整える仕組み
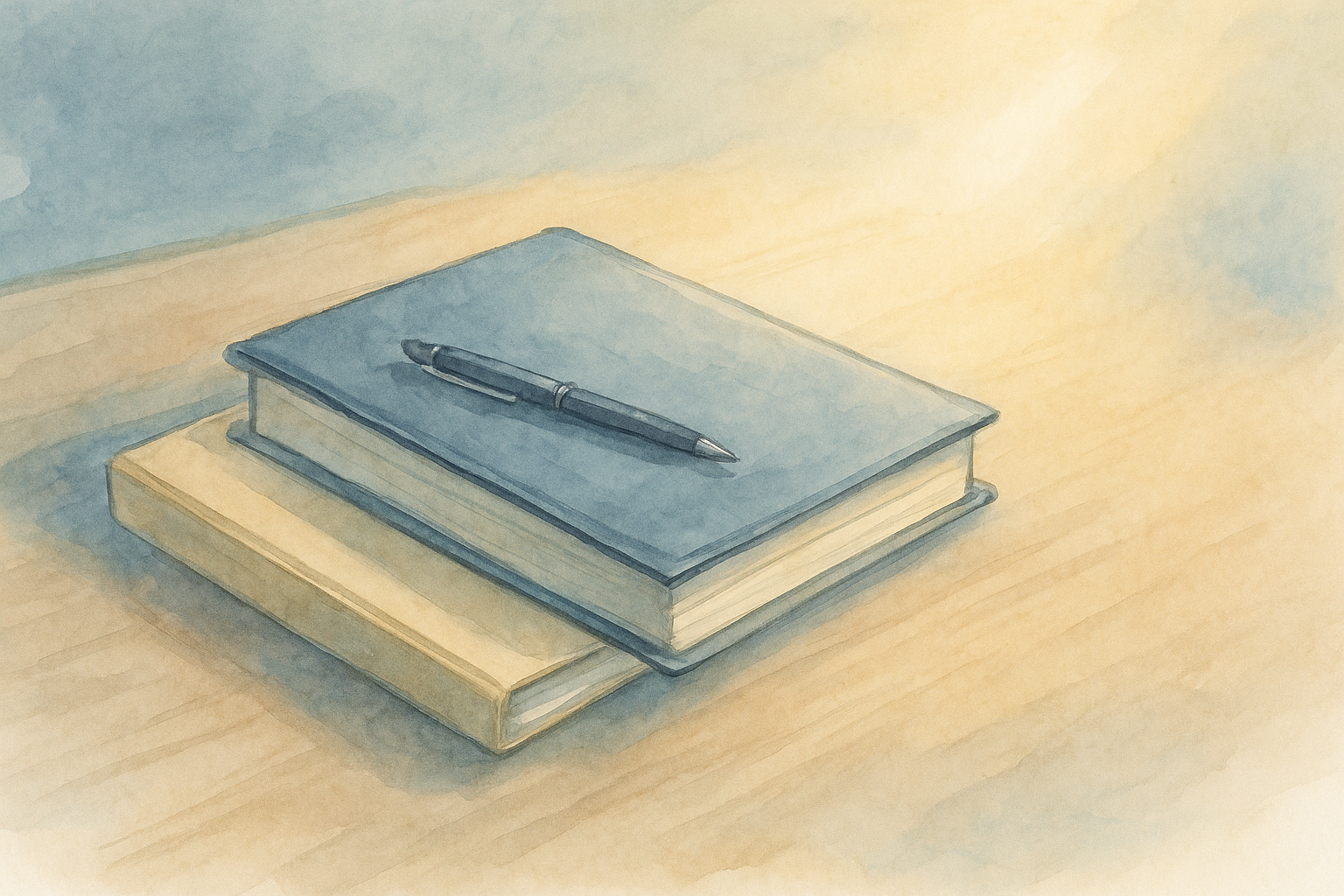
同じ財産が短い期間のうちに二度相続される。
それは家族にとって、悲しみが重なるだけでなく、税務の上でも複雑な現象です。
一度目の相続で課税された財産に、短期間で再び税がかかるのは、同じものに連続して負担が生じることになる────
その負担を調整のために設けられているのが相次相続控除です。
短期間に続く相続と「二重課税」の問題
父が亡くなり、母が相続する。
その数年後、母が亡くなり、子に財産が引き継がれる。
このように相続が短期間に続くと、
同じ財産が二度相続税の課税対象になることがあります。
税法は、こうした“時間の重なり”によって生じる負担を調整するために、
相続税法第20条で「相次相続控除」を定めています。
一次相続で納めた税額をもとに、
二次相続で重なった部分を控除する――
連続する課税の負担を緩和するための仕組みです。
相次相続控除のしくみと適用の場面
適用の場面と基本の考え方
相次相続控除は、「同じ財産が同じ財産が比較的近い時期(10年以内)に二度相続された」場合に使える制度です。
相続は本来、一度きりの出来事として設計されていますが、
高齢化や家族構成の変化などにより、最初の相続から数年のうちに次の相続が起こることがあります。
そうした「家族の時間が近接した相続」では、
同じ財産が続けて課税対象となり、結果として過重な負担が生じます。
相次相続控除は、この時間的な重なりによる課税の負担を調整し、
税の体系としての整合性を保ちながら、負担を一定の範囲におさめるために設けられた制度です。
適用される代表的な場面は、次のとおりです。
| 家族関係 | 相続の流れ | 控除が働く理由・意味 |
|---|---|---|
| 親子の連続相続 | 祖父が亡くなり父が財産を取得。その数年後に父も亡くなり、同じ財産が孫へ承継される。 | 世代をまたぐ相続が短期間に続くとき、同じ財産に連続して課税が生じる負担を調整。 |
| 兄弟・姉妹間の連続相続 | 兄が父の遺産を相続後、数年で兄が亡くなり、その財産が妹に移る。 | 家系内で短期間に財産が動くときの課税負担を調整。 |
| 同世代内での持分移転 | 親の遺産を兄弟二人が分けた後、短期間で一方が亡くなり、もう一方に持分が集中する。 | 同一世代間の財産移転でも、短期に続く場合は控除の対象となる。 |
※兄弟・姉妹間や同世代内の連続相続は、亡くなった方に配偶者や子がいない場合に発生します。
このようなケースでは、短期間に家系内で相続が続くため、相次相続控除の効果が比較的大きくなります。
適用のための条件(法的要件)
この制度が使えるのは、次の三つの条件をすべて満たす場合です。
① 前回の相続の発生から 10年以内 に次の相続が起きたこと
② 前回の相続で 実際に相続税を納めていること
③ 同じ財産が再び相続されたこと
この3条件を満たすと、二次相続の税額から一定額を差し引くことができます。
一見単純に見えますが、
「10年以内」の判定には1年未満の端数切捨てがあり、
また、一次相続で実際に相続税を納めていることが制度適用の前提となります。
その証明書類として申告書や納付書の写しを添付する義務はありませんが、
実務上は前回相続の申告書控・納付書控を保管し、
二次相続の申告時に確認できるようにしておくことが推奨されます。
📝 メモ:「数次相続」との違い
よく似た言葉に「数次相続(すうじそうぞく)」があります。
これは法務・登記の文脈でよく使われますが、
税務の現場でも便宜的に用いられることがあります。
ただし、法令上の制度用語ではなく、相次相続控除とは異なる概念です。
「数次相続」は、一次の相続が未分割のまま次の相続が発生し、
財産が二重に承継されてしまう“手続上の重なり”を指します。
一方の「相次相続控除」は、
同じ財産が短期間に二度課税される“税務上の重なり”を調整する制度です。
| 区分 | 意味 | 主な対象 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 数次相続 | 前の相続が未分割のまま次が発生(登記・分割上の重複) | 法務・登記 | 手続上の重なり |
| 相次相続 | 同じ財産に短期間で二度課税(税務上の重複) | 税務・申告 | 税負担の調整 |
つまり、「数次相続」は手続面の問題、
「相次相続控除」は税金計算上の調整。
どちらも“相続が連続して起きる”状況を扱いますが、
目的と扱う対象が異なります。
相似相続控除の計算のイメージ
相次相続控除の計算は、前回の納税額を基礎に、
経過年数と財産の引継ぎ割合を考慮して求めます。
控除額 = 前回納付税額 × (10 − 経過年数) ÷ 10 × (再取得財産 ÷ 前回課税財産)
この式は、一次相続で納めた税金のうち、
「時間的にも、財産的にも重なった部分だけを二次相続で差し引く」という考え方を表しています。
「(10−経過年数)÷10」は時間の重なりを示す係数で、
相続の間隔が短いほど控除が大きくなります。
「再取得財産÷前回課税財産」は財産の重なり具合を示す係数で、
前回課税された財産のうち、どれだけが再び相続されたかを反映します。
言いかえると――
前回納めた税金 × 時間の重なり(10年で薄れる) × 財産の重なり(どれだけ同じものか)
= “今回控除してよい金額”。
税法はこのように、時間と財産の重なりを数式で表し、
重複する課税を調整しながら、課税の整合性を保つ仕組みを作っています。
祖父が亡くなり、父が1億2,000万円の遺産をすべて相続し、相続税として120万円を納めました。
その5年後、父が亡くなり、生活費などで減った財産が8,000万円残っていました。
その8,000万円が孫に相続されました。
孫が父の相続を申告する際、
祖父の相続で父が納めていた税額をもとに相次相続控除を適用できます。
短期間に「祖父→父→孫」と相続が続いたことで、
同じ財産に二度課税される部分を調整する仕組みです。

祖父の相続でお父様が納めていた120万円を基礎に、
残っていた財産(8,000万円)は前回課税財産の約2/3にあたります。
経過年数5年の係数0.5を掛けると、120万円×0.5×0.67=約40万円。
これが今回の相次相続控除の目安になります。
つまり、祖父の財産が短期間で二度相続されたことで生じる二重課税の部分を、
今回の孫の相続で税額控除として調整する仕組みなのです。
実務上の注意点
相次相続控除を使うには、一次相続の申告書と納税明細の保存が不可欠です。
控除の基礎となる「前回税額」を確認できなければ、制度は使えません。
また、一次相続で配偶者の税額軽減を適用して税額ゼロだった場合は、
控除の基礎となる税が存在しないため、適用できません。
税額控除の連続──配偶者・障害者・未成年者
配偶者の税額軽減と相次相続控除の関係



父が亡くなったとき、配偶者の税額軽減を使って母は税金ゼロにしました。
でも母もまもなく亡くなって、あとから“配偶者の税額軽減を使わないほうが節税になったかも”って聞いたんです。



そうですね。
相次相続控除は“前回納めた税額”を基礎に計算します。
一次で配偶者の税額軽減を使って税額ゼロにすると、
二次では控除の基礎となる税が存在しないため、相似相続控除が適用できません。
もし一次で税が発生していれば、その税額をもとに二次で控除ができ、
結果的に家族全体の負担が少し軽くなることもあります。
障害者控除・未成年者控除の引継ぎと除外
相続が続いたとき、もう一つ注意すべきなのが障害者控除と未成年者控除です。
これらは「相続人の年齢・障害の状態」に応じて計算される個人単位の税額控除であり、
相続が二度起きても、一次で受けた控除は二次で再び使うことはできません。



たとえば、一次相続で障害者控除を受けた相続人がいたとしても、
二次相続ではその分を除いて計算します。
“一次で控除を受けた金額は除かれる”んです。



そうなんですか?また全額使えるのかと思っていました。



そこが落とし穴です。
障害者控除は年齢区分ごとの年数計算なので、一次で控除した年数分はもう残っていません。
未成年者控除も同じで、一次で未成年だった方が二次の時点で成人していれば、
控除の対象外になります。
この「控除除外」を忘れて二次で再計上してしまうミスは、現場でも多く見られます。
特に障害者控除は金額が大きく、誤ると数十万円単位の影響が出ます。
二次相続の申告時には、一次相続でどの相続人がどの控除を受けたかを必ず確認し、
その控除額を正確に除外すること。
そのためには、一次相続の申告書をきちんと保管し、
二次の申告時に必ず参照できるようにしておくことが大切です。
相続税の申告書は「そのときだけの書類」ではなく、
次の申告へとつながる“家族の記録”でもあります。
控除の履歴を引き継ぐ意識が、正確な連続相続の整理につながります。
税を整えるということ──記録の連続と備え
相次相続控除は、短い期間に続けて起こる相続で、
同じ財産に二度課税される負担を調整するための仕組みです。
けれども、これを使うには、前回の申告書や納付書、財産の明細など、
過去の記録が正確に残っていなければなりません。
一度の相続で完結することは少なく、
前回の手続きを確認しながら次を進めることになります。
記録が整っていなければ、本来受けられる控除を逃すこともあります。
税を整えるとは、計算を合わせるだけでなく、
これまでの経緯を正しく確認し、次へと確実につなぐこと。
相続を丁寧に記録することが、結果として最も確かな備えになります。