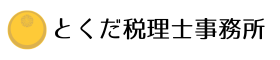面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
相続が続いたとき④:一次相続をうっかり申告していなかった場合

一次相続のあと、
「税額が出ないから申告しなくてもいい」と判断して手続きを終える方も少なくありません。
実際、基礎控除の範囲内であればその判断は正しく、申告の必要はありません。
ただし中には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用してはじめて税額がゼロになるケースもあります。
その場合は、本来は申告をして特例を適用すべきところを、
「結果がゼロだから申告不要」と誤解してしまった状態になります。

うちは最初の相続で税金がかからないって聞いたんで、申告しなかったんです。大丈夫ですか?



“かからない”理由によります。軽減や特例を使ってゼロにする場合は、申告が必要なんですよ。
このように一次の申告をしないまま次の相続を迎えると、
二次相続では「どの財産が一次で取得したものか」や
「本来どの特例を適用できたか」が確認できず、
税額の計算や控除の判断に整合が取れなくなることがあります。
とくに、民法上の遺産分割も十分に行われず、
「配偶者が1億6千万円以内なら申告はいらない」
といった理解のまま申告を省いていたケースでは注意が必要です。
このような場合、誰がどの財産を相続したかが税務上確定していないため、
二次相続で課税関係がずれてしまうことがあります。
一方で、遺産分割が申告期限までに成立しており、
財産の帰属関係が明確であれば、
期限後申告によって配偶者の税額軽減などの適用を整えることは可能です。
ただし、小規模宅地等の特例のように、
分割や申告の時期が要件とされている制度では、
期限を過ぎると特例を回復できない場合もあります。
つまり、問題は「分割が遅れたこと」そのものではなく、
本来は申告が必要だった一次相続を、分割も申告もあいまいなまま放置してしまったことにあります。
“申告しなかったこと”よりも、“整理しなかったこと”が、
次の相続の混乱を呼び込むのです。
一次相続の整理が不十分なまま残ると、
その影響が次の相続の手続や税務に及びます。
こうした連鎖こそが、本シリーズで扱う「連続する相続」の典型です。
なぜ「税額ゼロ」でも申告が必要だったのか
相続税の特例のうち、「申告していなければ適用できない」と定められているのはごく一部です。
代表的なのが 配偶者の税額軽減(相続税法19条の2) と 小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)。
これらは、申告書を提出してはじめて効力が生じる仕組みで、出さなければ制度そのものを使えません。



控除があるなら、申告しなくても自動でゼロになると思っていました。



配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は“申告して初めて使える”制度なんです。申告しなければ適用できません。
一方で、相次相続控除 や 障害者控除 など、
税額の計算上で考慮される控除は、申告そのものが要件ではありません。
これらは納税者が自分で計算し、控除を適用した結果、
課税価格が基礎控除以下となれば、そもそも申告義務が生じないこともあります。
ただ、この仕組みの違いは一般の方には分かりづらく、
「税額が出ない=申告不要」と判断してしまうことが少なくありません。
実際には、“申告して初めてゼロになる特例”と、“計算の結果ゼロになる控除”が混在しており、
制度の構造そのものが誤解を生みやすいのです。
とくに小規模宅地等の特例は、
申告期限までに分割が済んでいることが原則として必要で、
分割の時期が大きく遅れると適用できない場合があります。
仕組みは複雑ですが、ここで伝えたいのはただ一点──
「あとで申告すればいい」とは限らない制度だということです。
時間の経過で変わる──“放置された相続”の行方
本来は申告が必要だった一次相続を申告しないまま時間がたつと、
「いまからでも申告すべきか」「もう終わっているのか」という判断が難しくなります。
相続の間隔が短い場合は、期限後申告によって制度を整える余地がありますが、
長く放置されていると、事実関係の確認が難しくなり、
制度的にも整理できない部分が増えていきます。
たとえば、父の相続を申告しないまま数年後に母が亡くなった場合。
まだ期間が浅ければ、配偶者の税額軽減などを適用して期限後申告を行うことで、
税務上の関係を整え直すことができます。
しかし、十年近くが経っているようなケースでは、
評価や財産の出所をたどること自体が困難になり、
結果的に二次相続の申告で混乱が生じやすくなります。
相続税の制度には時効もあります。
通常は申告期限の翌日から5年、
仮装や隠蔽などがある場合は7年です(国税通則法70条)。
時効が完成してしまうと、たとえ自ら申告を望んでも受け付けてもらえません。
課税の手続きとしては区切りがつきますが、
それでも、一次相続の内容を整理しておくことには意味があります。
すでに次の相続が始まっている場合でも、
一次の財産の出所や評価を明確にしておくことで、
二次相続の計算や名義整理を正確に進めることができるからです。
期限後申告──制度を整えるという発想
一次相続の申告をしなかった場合でも、
まだ時間が浅ければ、期限後申告によって制度の秩序を整えることができます。
期限後申告とは、申告期限を過ぎてから行う正規の申告で、
単なる「追徴」や「罰則」ではありません。
むしろ、遅れてでも制度を正しい形に戻すための手続きです。



期限を過ぎてしまったんですが、もう手遅れでしょうか?



いいえ。むしろ今が整えるチャンスです。指摘を受ける前に自分から申告する方がずっと良いですよ。
期限後申告をすれば、配偶者の税額軽減などの特例も適用できる場合があります。
延滞税はかかるものの、誠実に整理を行えば加算税が軽減されることもあり、
税務署の対応も穏当なものになります。
とくに時効前の段階で税務署に指摘を受けると、
更正や賦課課税の対象となり、
本来自主的に申告していれば適用できた特例が認められない、という事態も起こり得ます。
期限後申告は、そうした不利な更正を避け、
自ら秩序を整え直すための申告なのです。
一次相続の整理は、次の相続を正しく始めるための土台
一次相続の申告をしないまま二次相続を迎えると、
本来なら一次で確定しているはずの財産関係や特例の適用状況があいまいなまま引き継がれます。
その結果、二次相続の申告で「どの財産を誰がいつ取得したのか」が不明確になり、
税務上の整合を取るのが難しくなります。



一次相続の整理を後回しにすると、二次相続の計算がどうしても複雑になります。
まず一次を整えることが、二次の正確なスタートになるんです。
一次相続をいま整理することは、過去を清算するためではなく、
次の相続を正しく始めるための手続きです。
期限を過ぎていても、一次の財産の出所や評価を明らかにしておくことで、
二次相続の課税計算や分割の方向性を明確にできます。
すでに二次相続が始まっている場合でも、
一次の財産の出所や評価を明確にしておけば、
二次相続の計算や名義整理を正確に進めることができます。
税理士の役割は、期限内の申告を支援するだけではありません。
連続する相続の途中から関与して、一次相続の内容を整理し、
次の相続の計算や名義整理を進めやすくすることも大切な仕事です。
相続という制度は、ひとつの申告で完結するものではなく、
世代をまたいでつながっていくものです。
その流れをきちんと整理しておくことが、
次の相続を正確に進めるための土台になります。
次の第5回では、
連続して起きた相続で課税が重なるのを防ぐ仕組み、「相次相続控除」を取り上げます。
一次相続の整理を怠ると、この控除が適用が難しくなることもあります。
「過去の申告が次の申告を決める」──
そのつながりを、制度の側から見ていきます。