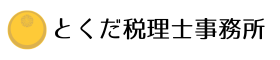面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
相続が続いたとき③:申告不要の相続こそ、次への備えを
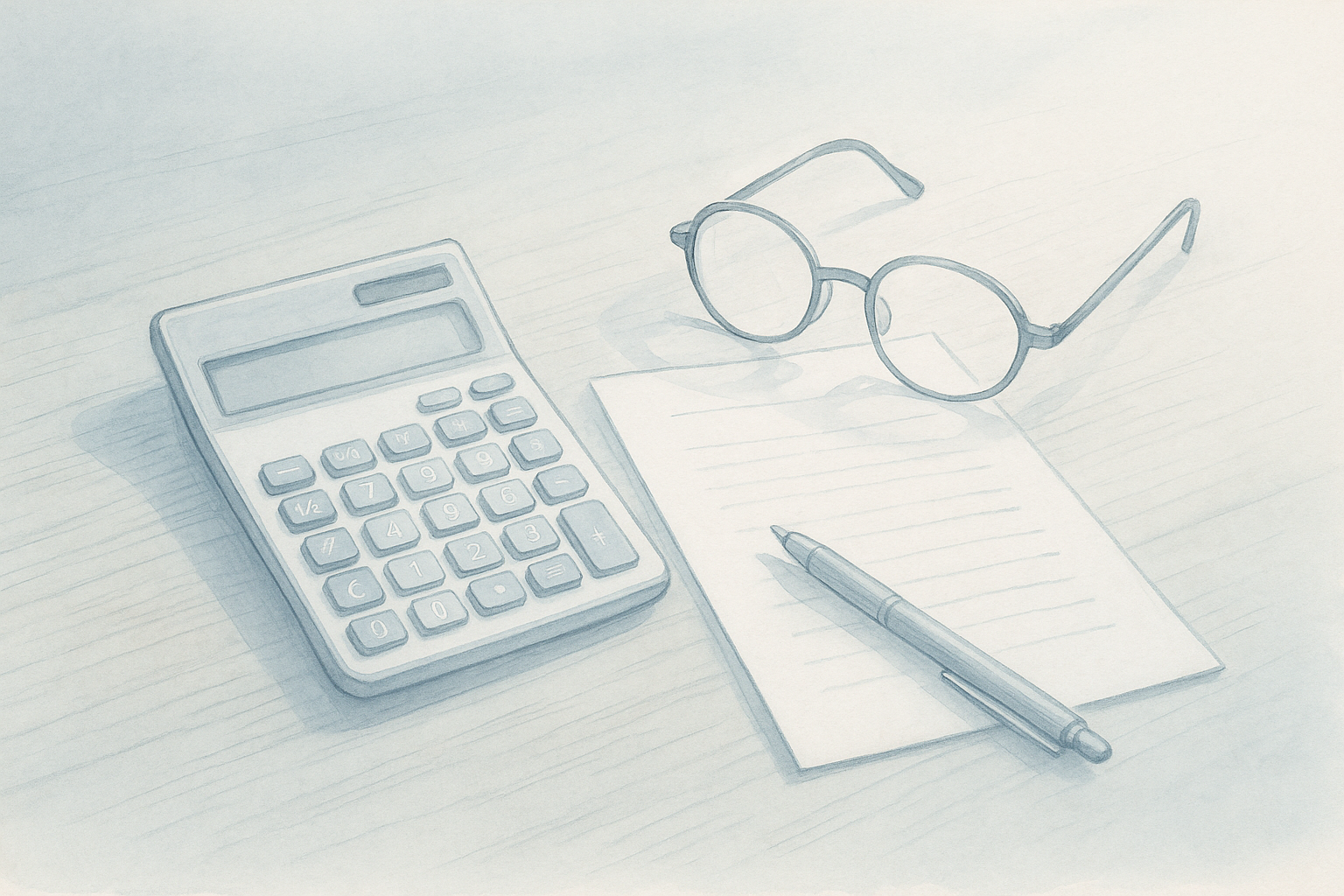
相続税申告をしなかったからといって、税務署が何も知らないわけではありません。
金融機関や保険会社などからは、一定の基準を満たす取引について「支払調書」等を通じて税務署へ情報が提供されるしくみになっています。
たとえば、生命保険金の支払調書や年金支払調書などが代表例で、平成30年1月以降は保険契約の変更内容も通知されるようになりました。
つまり、税務署は「申告がなかった相続」であっても、一定範囲の財産情報を把握しているのです。
不動産の登記情報については、法務局が管理しており、税務署に自動的に通知されるわけではありません。
ただし、必要に応じて税務署が職権で登記情報を照会できる制度があります。
このため、登記や名義変更を怠っている場合、後の相続や調査の際に確認を求められることがあります。

母の財産は少なかったので、税務署には何も伝わっていませんよね?



金額や内容によっては、銀行や保険会社から税務署に支払調書が提出されている場合もあります。整理をしておかないと、後で説明が必要になることもあります。
申告不要の根拠を短く記す/基礎控除ギリは安全申告も
最初の相続(一次相続)で相続税申告が不要だったからといって、
財産の整理をあいまいにしたままにしておくと、
次の相続(二次相続)で「財産が増えたように見える」ことがあります。
本来は母の遺産だった預金が、名義が変わっていなかったために父の財産として再計上され、
結果として相続税が多くなってしまうこともあります。
また、家族の間でも「これはどちらの財産だったのか」が分からなくなり、
二回目の相続の話し合いが複雑になることがあります。
ですから、完璧に調べなくてもいいのです。
どの口座を誰が使っていたかをメモに残すだけでも、
後の手続きと家族の負担を軽くできます。
相続税申告をしない判断をするときは、どこまで調べ、どう判断したかを簡単に記録しておくと安心です。
あとから新しい財産が見つかったり、評価の見直しで基礎控除を超えていたと分かることもあります。
そのときに慌てて説明資料を作るのは大変です。
最初の段階で「何を根拠に申告不要と判断したのか」をメモとして残しておくと、
後の対応が格段に楽になります。
基礎控除に近い場合は、税理士に相談して“安全申告”をしておくのも一つの方法です。
このあたりの判断の分かれ目については、次回の記事で詳しく解説します。
最初の相続での判断が、次の相続で再び問われる
一次相続で「相続税申告は不要」と判断しても、その判断が永続的とは限りません。
二次相続の際に、一次で整理しなかった財産や判断が再び問われることがあります。
たとえば、一次相続で「基礎控除内」と考えていた財産が、
二次相続で改めて評価した結果、控除を超えていたと判明することもあります。
税務署は、二次相続の調査の中で一次の内容を照会することがあるため、
一次相続の判断が“時間をまたいで検証される”のです。
相続税には除斥期間(時効)があり、原則5年、偽りや不正がある場合は7年です。
この期間内であれば、税務署が一次相続を遡って課税の可否を確認することがあり、
「終わったつもりの相続」が後に再検証されるケースも少なくありません。
この“時間の連続性”こそが、連続相続を難しくする要素です。
だからこそ、申告不要でも「どんな判断をしたか」「どんな資料を残したか」を
明確にしておくことが、後の相続を守る手続になります。
要否検討表を活用するという選択
一次相続で相続税申告が不要と判断した場合でも、
「相続税の申告要否検討表」を作成・提出しておくと、
財産の概要を整理でき、税務署にも一次相続の状況を共有できます。
この書類は、
「相続税申告が必要かどうかを検討した結果、今回は申告不要と判断した理由」
を示すための資料
であり、申告書を出さない代わりに、判断の経緯を明らかにする”ためのものです。
提出は義務ではありませんが、後日の二次相続の資料にもなり、説明責任を果たす意味でも有効です。
たとえば、現預金が数百万円ほどで、土地のような評価の難しい財産がなく、
足し戻しが必要な生前贈与もない場合は、
財産総額が基礎控除を大きく下回るため、要否検討表を出す実務的メリットはあまりありません。
けれど、土地の評価や名義預金、生命保険に関する権利など、
評価や性質の判断によって金額が変動する財産を含む場合は注意が必要です。
相続税は、網羅性――すべての財産をもれなく計上すること――が何より重要です。
自分では控除内と思っていても、見落とした財産の積み上げで基礎控除を超えることもあります。
そのため、基礎控除内だと感じていても、一度税理士に相談して要否検討表を作成してもらうのがおすすめです。
税理士が関与することで、財産の全体像が整理され、
「本当に相続税申告が不要で問題ないか」「将来の相続に備えた資料を残すにはどうするか」を
専門的に確認できます。
“資料を作る”という備え
相続税申告が不要な場合でも、財産の一覧や評価のメモを残しておくことは、
単なる事務作業ではなく、次の相続への備えです。
誰がどの財産を引き継ぎ、どんな考えで整理したのか――
その記録を残しておくことは、
次の相続で家族が迷わないための「道しるべ」になります。



相続税申告しなくても、ここまで整理する意味がありますか?



はい。税金のためというより、将来の家族の安心のためなんです。
相続の整理は、“今を守るための手続”であると同時に、
未来へと続く家族の準備でもあります。
税理士の関与によって、その記録は客観性を持ち、
次の相続や財産承継の際にも信頼できる指標になります。
まとめ:申告不要でも、整理が次の相続を守る
相続で手続きをしなかったことも、税務上は“申告不要と判断した”という記録になります。
その判断の根拠を整理しておくことが、次の相続を正確に進める土台になります。
高齢化が進み、複数の相続が短期間に重なる家庭も増えています。
そうした時代では、一次相続での小さな曖昧さが、
次の相続で思わぬ手間や税負担につながることがあります。
申告不要だった相続こそ、後のために整理しておく価値があるのです。
財産の全体像を把握し、判断の経緯を記録に残しておくことは、
後の調査や家族間の混乱を防ぐうえで効果的です。
財産が明らかに基礎控除を大きく下回り、特にめぼしい資産がない場合を除けば、
税理士に相談して「相続税の申告要否検討表」を作成してもらうのが安心です。
要否検討表を整えておけば、後日新たな財産が見つかったときにも、
一次相続での判断を説明する材料になります。
税理士は、相続税の申告が不要な場合でも、
財産の整理や要否検討表の作成を通じて、
次の相続で慌てないための準備を支援できます。



弊所でも、そうした整理のご相談を承っています。
要否検討表の作成や財産の棚卸しなど、次の相続を見据えた準備を一緒に進めていくことが可能です。