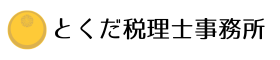面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
相続が続いたとき①:税理士の視点で見る、連続する相続の全体像
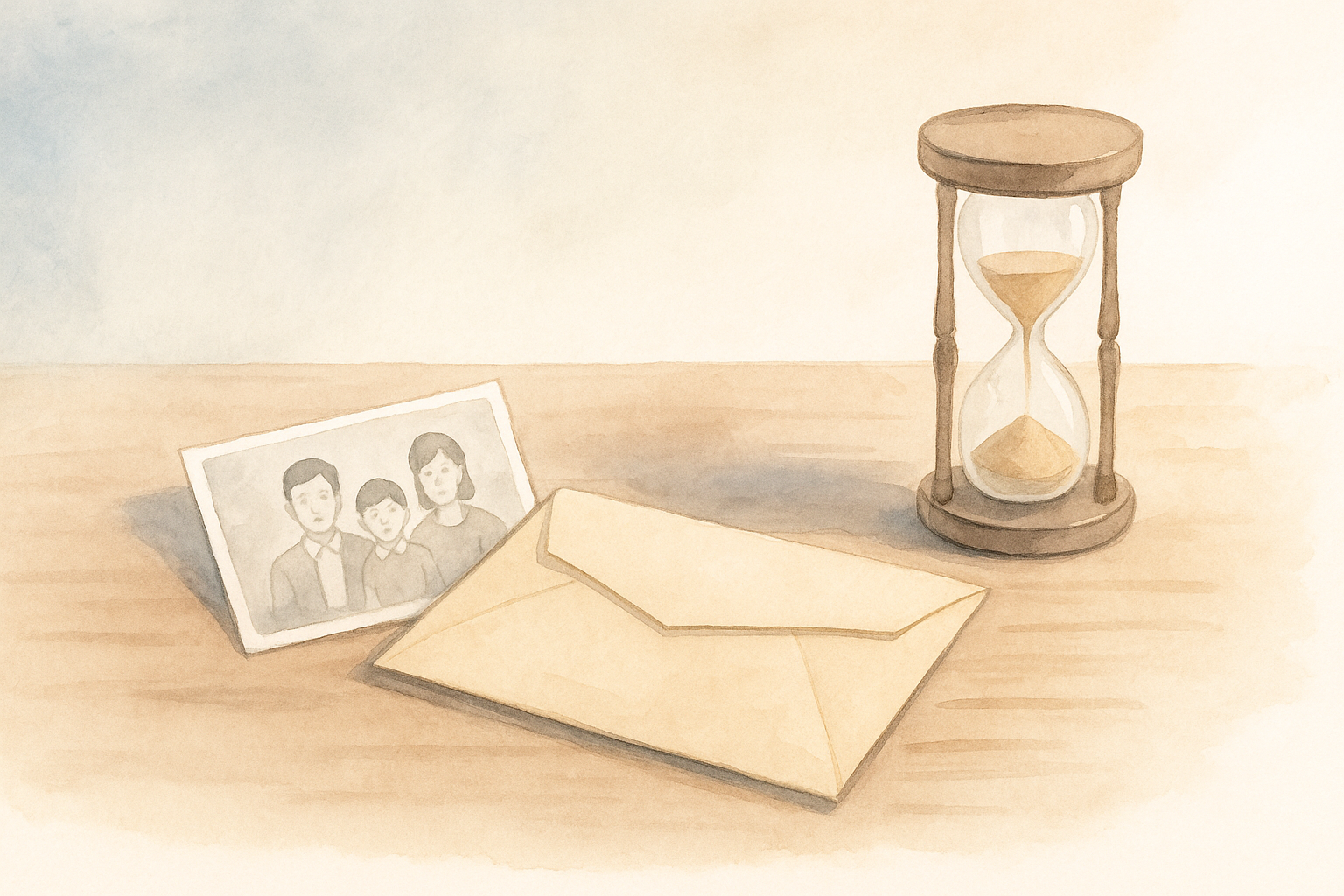

母の相続が終わらないうちに、父まで亡くなってしまって……。
こんなふうに続くことって、よくあるんですか?



あります。相続は、一度きりで終わることもあれば、家族の時間の流れの中で続いて起こることもあります。
相続が「続く」という現実
相続は一度きりの出来事と思われがちですが、現実には「続けて起こる」ことがあります。
両親が数年のうちに相次いで亡くなる。
あるいは、最初の相続の整理が終わらないうちに、次の相続が起きてしまう。
こうした「連続する相続」は、いまの日本では決して珍しくありません。
税理士として現場を見ていると、一つの相続をどう設計するかが、次の相続の負担を決めてしまう場面が多くあります。
制度の上ではそれぞれ独立した「別の相続」でも、
家族にとっては、ひと続きの時間の中で起こる連鎖的な出来事です。
長寿化と家族の時間の変化
つては、親の相続を終えてから子が亡くなるまで、二十年、三十年という時間があるのが普通でした。
しかしいまは、親が九十代、子が六十代・七十代という時代。
その距離がぐっと縮まり、親と子の相続が数年以内に続くこともめずらしくありません。
しかも、同居していた親の預貯金や不動産が入り混じっていたり、
介護費用を誰がどの口座から負担していたのかが曖昧だったりする。
一次の相続で整理しきれなかった財産が、そのまま次の相続の対象になってしまう──そんな事例が年々増えています。
手続の途中で次の相続が起きることもあります。
家庭裁判所の後見手続きを待っているうちに、別の相続人が亡くなってしまう。
分割協議がまとまらないまま次の相続を迎える。
制度の上では「別件」でも、実際の家族の時間は明らかに重なっています。
そして、夫婦のあいだで相続が続くケースも少なくありません。
昔から、どちらかが亡くなると、ほどなくしてもう一方の相続が起きることはありました。
近年は、夫婦だけで暮らす高齢世帯が増えたこともあり、
配偶者を失ったあとに体調を崩したり、気力を失ってしまったりして、
続けて相続を迎えるご家庭が目立つようになっています。
「夫婦が寄り添うように亡くなる」──その静かな現実を前にすると、
相続という制度の「区切り」よりも、家族の時間の「つながり」を意識せざるを得ません。
相続は、法的には「起点」と「終点」が定まる出来事ですが、
現実には、家族の記憶と感情の流れの中に続いていくものです。
「一度きり」ではなく「つながっている」相続へ
税務の世界では、相続は発生のたびに計算が区切られます。
しかし、実際には、その区切りのあいだに確かなつながりがあることを感じます。
一次相続で、誰がどの財産を取得したか。
その評価をどうしたか。
名義をどう整理したか。
それら一つひとつの判断が、次の相続の“出発点”になります。
理想を言えば、一次相続の時点で、次を見据えた整理をしておくことが望ましい。
けれど、実際にはそうはいかないことも多いのです。
「税金がかからないなら、しばらくそのままでいいだろう」
「書類をまとめるのが大変で、つい手をつけられない」
そんなふうに一次相続を“途中のまま”にしておいたり、
あるいは手続そのものに着手できないまま時間が過ぎてしまったりすることもあります。
そして、ようやく落ち着いて整理しようと思った頃に、次の相続が起きてしまう──。
二つの相続が重なると、書類の整理も気持ちの整理も追いつきません。
どちらの名義を先に動かすのか、財産の範囲をどう分けて考えるのか。
過去と現在が入り混じり、手続が絡み合っていく。
それが、「連続する相続」がもっとも重たく感じられる瞬間です。
けれど、いまからでも遅くはありません。
二つを分けて考えるよりも、ひと続きの流れとして整理していくほうが、むしろ分かりやすい。
まずは一次相続の状況を整理し、そこから次の相続をどう重ねていくかを順番に整えていけば、道筋は見えてきます。



母の相続がまだ終わっていないのに、今度は父まで亡くなってしまって……。もう何から手をつければいいのか分からないんです。



そう感じられるのは自然なことです。相続が重なると、誰でも混乱します。けれど、慌てなくて大丈夫です。
二つの相続を別々に考えるよりも、流れを一つにして整理していきましょう。
相続は、人生にそう何度も経験するものではありません。
けれど、いまの日本では「一度きり」とは言えなくなりつつあります。
本シリーズでは、短期間に相続が重なるときの手続・税務・法務を、税理士の視点から整理し、家族の負担を軽くする考え方をお伝えしていきます。
次回は、「一次相続が終わらないうちに次の相続が起きたらどうなるのか」──
未分割のまま進む“連続する相続”の仕組みを、実際の事例を交えて解説します。