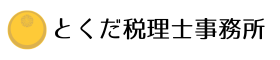面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
税務調査が来にくくなる?──“書面添付”で変わる相続税申告の安心度

相続税の申告を終えても、「あとで税務署から連絡が来たらどうしよう」と不安を抱く人は少なくありません。
じつはその不安を、制度の力で小さくできる方法があります。
それが、税理士だけが利用できる「書面添付制度」。
正しく使えば、税務署からの信頼そのものを申告書に添えることができ、結果的に税務調査が来にくくなる仕組みです。
この記事では、書面添付制度の仕組みと、相続税申告における実際の効果を、専門家の視点からわかりやすく解説します。
税務調査は「運」ではない──書面添付制度が信頼を左右する
相続税の実地調査率は、令和5事務年度で約10.6%(国税庁「相続税の調査等の状況」)。
文書照会などを含めると、全体ではおおむね15〜20%前後に達します。
「うちは大丈夫」と思っていても、調査を免れるかどうかは単なる運ではありません。
税務署が重視するのは、申告内容がどれだけ検証され、根拠をもって作られているかです。

きちんと申告していても、調査に入ることがあるのは、どうしてなんでしょう。



税務署は、数字の裏付けがきちんと取れているかを気にします。書面添付は、その確認の流れをきちんと伝えるための仕組みなんです。
税務の現場では、“どのようなプロセスで数字が導かれたか”が最も問われます。
この信頼の仕組みとして位置づけられているのが、書面添付制度です。
書面添付制度とは?──税理士法第33条の2に基づく“信頼の証”
書面添付とは、税理士が「どのような資料をもとに、どんな検討を行ったか」を文書で明示する制度です。
根拠は税理士法第33条の2(2025/4/1施行改正予定)。
「税理士は、依頼を受けて作成した申告書その他の税務書類について、その内容を確認し、意見を記載した書面を添付して提出することができる。」
この書面は申告書とともに税務署に提出され、税務署はそれをもとに申告の妥当性を確認します。
国税庁の運用上、書面添付がある場合は調査の前に税理士への「意見聴取」(税理士法第35条)が行われます。
ここで疑問点が解消されれば、実地調査そのものが省略されることもあります。



書面ひとつで、そんなに違うんですか?



税務署も、根拠や経過がきちんと示されていると安心するんです。信頼は、そうした確認の跡を“見える形”にしてこそ伝わります。
書面添付は単なる“書類の追加”ではなく、信頼の構造を制度化したものです。
税務署にとっても、疑問点を早期に整理できる合理的な仕組みなのです。
自分で申告する人は使えない──税理士申告だけの特典
この制度は「税理士法」に基づくものであり、ご自身で作成した申告書には添付できません。
どれほど丁寧に書いても、税務署から見れば“検証プロセスが不明”だからです。



自分で申告しても、丁寧に作れば大丈夫なんですよね?



もちろん丁寧さは大切です。でも、税務署からは“どう確認したか”までは見えにくいんです。書面添付は、その確認の過程を伝えるための制度なんですよ。
税理士が書面添付を行うことで、申告内容に第三者の専門的保証が加わります。
それは、税務署に対して「この申告は、検証を経ている」というサイン。
信頼は、気持ちではなく、確かめた跡を“書面という形”で残すことでつくられます。
税務調査が来にくくなる理由──意見聴取という“前段階”
税務署は、書面添付のある申告についてはすぐに実地調査を行いません。
まず税理士に対して「意見聴取」(税理士法第35条)を行い、内容に疑義がなければ調査を省略する運用です。



つまり、調査の前に説明の機会があるんですね。



そうです。書面添付があると、まず“意見聴取”という、税務署と税理士がきちんと話し合う場が設けられるんです。
税務署はまず書面を精査し、必要に応じて税理士を呼び、添付内容の考え方や確認の経過について説明を求めます。
これが、税理士法第35条に基づく「意見聴取」という正式な手続です。
ただ、書面に十分な説明が記載されていれば、税務署の確認の段階で疑問が解けて、意見聴取そのものが行われないことも多くあります。
実地調査は、疑問点を現場で確かめるための検証ですが、意見聴取は書面の内容について税理士が説明を行う場です。
双方が疑問点を整理し、理解をすり合わせることで、調査に至らずに済むこともあります。
そしてもう一つ重要なのは、この意見聴取で誠実に説明し、自主的に修正を行った場合、
通常10%前後かかる過少申告加算税が課されない(0%)扱いになることもあるという点です。
制度として、誠実な説明を評価する仕組みが設けられています。
書面添付の“当初申告限定”ルール
注意したいのは、書面添付が使えるのは当初申告のときだけという点です。
書面添付は、当初の申告書に添付して提出することが前提です。
原則として、申告書を出したあとに書面だけを追加で提出することはできません。
修正申告や期限後申告では適用されません(国税庁「書面添付制度の取扱要領」令和5年版)。



あとで添付することはできないんですか?



できないんです。書面添付は“申告書に添えて出す”のが決まりで、あとから足すことはできません。だからこそ、最初の申告で制度を使うことが、安心を形にできる大事なタイミングなんです
初回申告こそ、誠実さを可視化する最大の機会。
後から「添付しておけばよかった」と思っても、もう制度上は間に合いません。
だからこそ、相続税の申告を依頼するときに、税理士が書面添付に対応しているかどうかを確認することが大切です。
もし調査になっても──防御力が違う
万が一、調査に発展しても、書面添付のある申告は対応の構えがまったく違います。
税理士はすでに論点を整理し、根拠資料や判断経過を記録に残しています。
そのため、調査の場では「何を、どのような考え方で処理したか」を説明するだけで済むことが多いのです。



添付しておけば、調査もこわくないんですね。



添付があると、考え方や根拠がすでに書面で示されています。だから、調査が“対立”ではなく、“確認”として進むことが多いんです
たとえば、不動産の評価や同族会社株式の算定など、判断に幅がある部分では、
税理士があらかじめ検討の過程を明示していることで、調査官もその判断根拠を尊重します。
「どんな考えでこの数値を採用したのか」が記録されていること自体が、調査対応の“盾”になるのです。
添付書面は、申告の段階で築いた信頼を、後になっても守ってくれる。
つまり、書面添付は“事前の備え”であり、同時に“事後の防御”でもあるのです。
信頼の記録は、時間を越えて納税者を守る仕組みとして働きます。
それが、この制度の底に流れる静かな哲学です。
書面添付を行う税理士を選ぶ価値
現実には、書面添付を行う税理士は全体の約2割強しかいません。
制度の重みを理解し、検証と説明に責任を持つ姿勢の表れです。



添付する税理士って、少ないんですね。



ええ。書面添付は手間がかかる分、必要な人に的確に使うのが現実的なんです。
添付を行うには、資料を確認し、検討の経過をまとめる手間がかかります。
だからこそ、どんな申告にも一律で使うものではなく、内容を見て判断します。
書面添付は、調査の可能性が高いときや論点が複雑なときに、申告の根拠を整理しておく方法です。
制度を使う目的は、調査を避けることではなく、判断の過程を正しく伝えること。
そうした考え方を持つ税理士が、書面添付を上手に使いこなしています。
書面添付の「デメリット」──誠実さの裏にある“責任とコスト”
書面添付は信頼を高める制度ですが、税理士にとっては相応の手間と責任を伴います。
添付書面を作るには、相続財産の根拠資料をすべて確認し、評価方法や判断の経過を文書にまとめなければなりません。
これは単なる“形式”ではなく、「どのような検討を行ったか」を第三者として明示する作業です。
書面添付は確かに安心を生みますが、その分コストもかかります。
調査リスクの高い事案(不動産評価や名義預金など)では効果が大きい一方、
内容が明快で争点の少ない申告では、必ずしも必要とはいえません。
また、添付をした税理士は、意見聴取や調査時に自らの判断について説明責任を負うことになります。
つまり、信頼を「請け負う」行為でもあるのです。
実際には、書面添付を行っている税理士はまだ限られています。
制度の手間や責任の重さから、使わずに済ませる事務所も少なくありません。
書面添付は「誰にでも」ではなく、「制度の効果が大きい人に」選んで使う性格のものです。
弊所でも同じ考えに立ち、書面添付は別料金のオプションとして位置づけています。
すべての申告に一律で付けるのではなく、
- 不動産や非上場株式を含む複雑な財産構成
- 名義預金など、調査で争点となりやすい内容
といったケースを中心に、必要性を個別に判断しています。
書面添付は、申告のあとも安心して過ごしていただくための制度です。
税務署に対して、どのような資料をもとに、どんな判断をしたかを明確に残すことで、申告後のトラブルを防ぎます。
費用もかかりますが、それは“安心を制度で支える”ための仕組みです。
大切なのは、「書面添付制度を利用することで、安心が続く」という実感を相続人の皆様に持ってもらうことです。
書面添付は“信頼の証”であって、“免罪符”ではない──形だけの添付は逆効果になることも
書面添付は確かに、税務署からの信頼を高める強力な制度です。
しかし、その信頼は“形式”ではなく“中身”によって支えられます。
形だけ書面を付けても、実質が伴わなければ意味がありません。



全部の申告に書面添付をつければ安心じゃないですか?



そう思われがちですが、大切なのは“付けること”より“どう書くか”なんです。形よりも中身に意味があります。
実際、すべての申告に一律で書面添付を行う税理士事務所もあります。
けれども、書面添付は「信頼の証」であって、「免罪符」ではありません。
中身の伴わない書面は、税務署に「本当に確認しているのか」と逆に疑問を持たれることもあります。
国税庁の運用要領でも、「記載内容に不備・形式的な記載があるものは意見聴取省略の対象としない」と明示されています。
書面添付を行うには、財産の根拠資料を一つずつ確認し、評価や判断の経過を文書化する必要があります。
つまり、税理士にとっては「時間・責任・リスク」を伴う作業です。
添付書面に誤りがあれば、税理士はその責任を問われる可能性もあります。
そのため、どんな申告にも一律で添付することが、かえって制度の意図を薄めてしまうこともあります。



“必要なときに、責任をもって添付する”のが正解、と私は考えています。
書面添付は、調査リスクが高い案件や、論点の多い申告でこそ効果を発揮します。
一方で、財産構成が明快で争点の少ない事案では、費用に見合う効果が小さいこともあります。
だからこそ、弊所では「すべての方に勧める」のではなく、本当に必要な人にだけ、丁寧に説明したうえでお勧めする。それが、誠実な税務支援のあり方だと考えています。
まとめ──安心は、制度と人の両方から生まれる
どんな制度にも、光と影があります。
書面添付もまた、使い方を誤れば「安心の証」ではなく「形だけの飾り」になってしまう。
だからこそ大切なのは、制度を知ったうえで、正しく使うこと。
信頼を“制度任せ”にせず、人の誠実さと制度の力を両輪にすることです。
書面添付制度は、税務調査を魔法のように消すものではありません。
しかし、誠実に作られた申告を、正当に評価してもらうための制度です。
税理士が検証し、記録し、説明する。
その積み重ねが「信頼される申告」を形づくります。



結局、書面添付制度といっても、使い方次第で安心の形が変わるんですね。



ええ。制度を生かして信頼を形にするのは、私たち税理士の仕事なんです。
税務調査の不安を減らす確かな方法は、書面添付制度を理解し、正面から使いこなせる税理士と組むこと。
それが、「安心で終わる相続税申告」への最短ルートです。
本記事は、2025年4月1日施行予定の法令および令和5年度の国税庁・財務省公表資料に基づいて執筆しています。
最新の運用状況は、国税庁公式サイトの「書面添付制度に関する取扱要領」等をご確認ください。