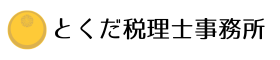面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
遺産分割が決まらないまま相続税の期限がくるとどうなる?──“未分割申告”で守る最善策

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内。
数字だけ見ると長く感じますが、実務では驚くほど短い期間です。
財産の洗い出し、預貯金残高の確認、不動産の評価、戸籍の収集。
これらを整えたうえで家族全員で遺産分割協議を整えるとなれば、10か月はあっという間です。
- 家族の中に認知症の方がいて成年後見の手続きを待っている。
- 相続人が海外にいて書類のやり取りに時間がかかる。
- 不動産の境界確定や名義整理が難航している。
こうした理由で期限に間に合わないのは、「もめている家庭」だけの話ではありません。
むしろ、誠実に準備を進めている家庭ほど起こり得る現実です。
けれども、税法の期限は動きません。
どんな事情があっても、10か月という時間は淡々と過ぎていきます。
では、期限までに分割が終わらないとき、どうすればいいのでしょうか。
分割が終わらなくても申告できる──“未分割申告”という制度

遺産分割が終わっていないのに、相続税の申告を出しても大丈夫なんですか?



はい。法定相続分で仮に申告すれば、期限を守ることができます。
相続税は「期限内申告」が原則です。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税といった附帯税が課されるおそれがあります。
しかし、分割が間に合わない場合でも、
法定相続分で仮に申告することが認められています。
これが「未分割申告」です。
内容は暫定でも、期限だけは守る。
この行動こそが、税法が求める「誠実な対応」です。
未分割申告の主な目的
- 無申告加算税や延滞税を回避する
- 「期限を守る誠実な姿勢」を示す
- 分割成立後に特例を適用できる余地を残す
💡補足:未分割申告をしておかないと「無申告扱い」になることも
税務署は、金融機関や法務局などから提出される資料により、被相続人の財産状況を把握しています。
そのため、相続財産が基礎控除額を超えているにもかかわらず申告が確認できない場合には、
「無申告の可能性がある」と判断されることがあります。
相続税の申告を期限までに行わなかった場合、
延滞税や無申告加算税が課されることがあります。
また、後日、税務署から申告内容や分割状況の確認を求められることもあります。
未分割のままでも、法定相続分で仮に申告しておけば、
「期限を守って誠実に対応している」と明確に示すことができます。
この“期限を守る姿勢”こそが、税務署との信頼関係を築くうえで最も重要です。
特例はどうなる?──配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例の適用の整理
未分割申告をすれば、期限は守れます。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例といった主要な優遇は、一旦保留されます。
これは「罰」ではなく、「公平性を保つための仕組み」です。
相続税法第19条の2(配偶者の税額軽減)や
租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等の特例)は、
いずれも「誰がどの財産を取得したか」が確定していることを前提にしています。
したがって、分割が終わっていない段階では、これらの特例を適用できません。
配偶者の税額軽減(相続税法第19条の2)
配偶者が取得する財産について、
1億6,000万円または法定相続分までの部分を非課税とする制度です。
未分割中は適用できませんが、
申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば、
分割成立後に更正または更正の請求を行うことで特例を回復できます。
つまり、「当初申告で適用する」よりも、
「分割成立後に更正で適用を取り戻す」というのが制度の本筋です。
小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条の4)
被相続人の自宅や事業用地を評価額から最大80%減額できる特例です。
この制度も、未分割中は適用できません。
ただし、申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、
分割成立後に更正または更正の請求により適用を回復できます。
さらに、この条文の第7項には「相続税の申告書(期限後申告書および修正申告書を含む)」と明記されています。
このため、期限後申告であっても分割見込書を添付して提出すれば、
特例適用が認められる可能性があるという解釈もあります。
もっとも、国税庁の通達や質疑応答事例では「申告期限までに分割見込書を添付していること」を前提にしており、
期限後申告での添付を常に有効とまでは明示していません。
したがって、**実務上は“可能性がある(△)”が、“保証されるわけではない”**という扱いになります。
安全に運用するには、やはり期限内に分割見込書を提出しておくことが最も確実です。
💡比較表:期限を守るか、分割を待つか──2つの申告判断の違い
分割が間に合わないとき、
「きちんと分け終えてから申告したい」という気持ちは自然なことです。
しかし相続税法は、期限を守る姿勢をまず評価するしくみになっています。
期限後に分割してから申告する方法も、制度上は可能です。
けれども、その場合は延滞税・加算税の対象になりやすく、
小規模宅地等の特例など、一部の優遇を使えないおそれがあります。
一方で、分割が整わなくても、法定相続分でいったん申告し、
「分割見込書」を添付しておけば、後日分割が成立したときに
特例を適用できるよう設計されています。
| 項目 | 期限内・未分割申告(期限を誠実に守る申告) | 期限後・分割済み申告(分割成立を待ってから出す申告) |
|---|---|---|
| 申告のタイミング | 期限を守って提出(10か月以内) | 分割成立後に期限を過ぎて提出 |
| 分割の状況 | 協議未了(法定相続分で仮申告) | 協議成立済(内容確定) |
| 無申告加算税・延滞税 | なし | 原則あり(10〜15%+延滞税) |
| 配偶者の税額軽減 | ×(分割成立後に更正の請求で回復可○) | ○(分割済で要件充足) |
| 小規模宅地特例 | ×(分割見込書を出しておけば更正の請求で回復可○) | △(分割済なら○。未分割でも分割見込書を添付すれば条文上は適用余地あり) |
| 税務署の印象 | 「期限を守った誠実な対応」として受け取られやすい | 「無申告扱い」に近く、説明を求められやすい |
| 手続きの流れ | 期限内に申告 → 分割見込書添付 → 後日更正の請求で特例適用 | 期限後に申告 → 分割済なら特例可。未分割なら判断分かれる |
| 制度の評価 | 「完璧」よりも「誠実な期限遵守」を重んじる制度設計 | 延滞税の負担と特例適用の不確実性が残る |
制度は、完璧よりも「誠実な期限遵守」を重んじます。
期限後申告でも配偶者控除が適用される場合はありますが、
小規模宅地特例など、期限を過ぎると原則使えない制度もあります。
つまり、分割が間に合わなくても期限を守るほうが、
後から修正できる余地が広い。
これが、最も安全で現実的な判断です。
💬誤解から“損”をしてしまう人がいる
ときどき「期限を過ぎても特例は使える」という説明を見かけます。
これは配偶者控除には当てはまりますが、小規模宅地特例には必ずしも当てはまりません。
小規模宅地特例は原則として申告期限内に分割が確定していることが前提であり、
後から特例を適用し直すことができるルートの中心は、
「申告期限までに分割見込書を提出していること」(租特法69条の4第6項)です。
一部では、条文上「期限後申告書を含む」とあることから、
期限後に分割見込書を添付しても特例が認められる余地があるとの解釈もありますが、
これは実務上の運用が分かれるグレーゾーンです。
確実に権利を確保したい場合には、必ず期限内に分割見込書を添付しておくこと。
これが最も安全で、後悔しない選択です。
分割見込書で救済される仕組み
申告期限までに分割が終わらない場合でも、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告期限までに提出しておけば、
後から特例を回復できる制度があります。
根拠条文は次のとおりです。
- 相続税法第19条の2第6項(配偶者の税額軽減)
- 租税特別措置法第69条の4第6項(小規模宅地特例)
これらはいずれも、申告期限までに分割見込書を提出し、
3年以内に分割が成立した場合には、更正または更正の請求により特例を適用できると定めています。。



分割が3年以内に決まれば、特例の適用を取り戻せるんですか?



はい。申告期限までに分割見込書を出しておけば、分割が整った時点で特例を回復できます。
分割見込書には、「未分割の理由」と「今後の見込み」を具体的に書きます。
たとえば「成年後見人選任中」「家庭裁判所調停中」など、合理的な事情を明示します。
この書類を期限までに添付しておくことが、
後日、分割が整ったときに特例を適用し直すことができる権利を確保する最も確実な方法です。
期限を過ぎて提出した場合、法令上は要件を満たさない扱いになります。
実務上は、期限後申告時に分割見込書を添付しても、
税務署が柔軟に扱う場合もあります。
しかしその判断は統一されておらず、認められない可能性もあるため、
期限内提出を原則とするのが安全です。
なお、申告期限後3年を経過しても、家庭裁判所の調停や審判、訴訟などが継続している場合には、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで延長が認められる場合があります。
承認を受けた日の翌日から4か月以内に分割が成立すれば、特例の適用が認められます。
🕒補足メモ:分割成立後の更正請求期限
分割が成立したときは、特例の適用を回復するために更正の請求を行います。
この手続きは、分割成立日の翌日から4か月以内に行う必要があります。
やむを得ない事情による延長
申告期限後3年を経過しても、家庭裁判所の調停や審判、訴訟などが継続している場合には、
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することで延長が認められる場合があります。
承認を受けた日の翌日から4か月以内に分割が成立すれば、特例の適用が認められます。
🕒補足メモ:二つの「4か月ルール」
どちらも“4か月”ですが、使う場面と起点がまったく違います。
・分割が成立した場合は、成立日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。
→ 未分割のまま期限内申告をした人が、あとで特例を「回復」するための手続です。
・「やむを得ない事由」で承認を受けた場合は、承認日の翌日から4か月以内に分割を成立させる必要があります。
→ 長期の紛争などで3年を超えてしまった人が、特例適用の“最後のチャンス”として使う仕組みです。
同じ「4か月」でも、前者は“請求の期限”、後者は“分割の期限”。
期限を超えると特例を使えなくなるため、分割成立や承認の連絡を受けたら、早めに税理士へ相談しましょう。
税務署は“誠実な申告”を見ている
税務署は未分割申告を「怪しい」とは見ません。
ただし、「まだ変動の余地がある申告」として慎重に観察します。
そのため、添付書類の丁寧さが後の印象を大きく左右します。
特に、税理士法第33条の2に基づく「書面添付制度」は、
未分割申告の信頼性を高める最も有効な方法です。
税理士が独立した立場で、分割未了の理由と見通しを記録して添付しておけば、
税務署はそれを“誠実な仮申告”として扱いやすくなります。
さらに、意見聴取の段階で説明が尽くせれば、調査に発展せず終結することもあります。
後日の更正請求時にも整合性が保てるため、書面添付は信頼の土台になります。
期限を守ることが最大の防御
相続税の申告は、数字を並べるだけの作業ではありません。
そこには、期限を守るという手続の誠実さが問われています。
人にはそれぞれ事情があります。
介護、病気、後見、海外──どれも現実の生活の一部です。
それでも税法は、「期限を誠実に守ろうとする人」を前提に設計されています。
分割が間に合わないときは、「未分割申告」という方法で、
「いまはできないけれど、必ずやる」という意思を形にして期限内に示す。
この行動こそが、制度が想定している“誠実な対応”です。
そして、その誠実さを示した人には、後日、特例を回復できる仕組みが備わっています。
分割見込書を提出していれば、分割成立後に更正や更正の請求を通じて、
配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用し直すことができます。
税法は冷たく見えるかもしれません。
けれども、本当に誠実な人を見捨てないようにつくられています。
誠実とは、完璧であることではなく、
限られた時間の中で、約束を守ろうとする姿勢のこと。
未分割申告は、その誠実さを制度の中で伝えるための仕組みなのです。
🪶 まとめ
- 分割が間に合わなくても「未分割申告」で期限を守れる
- 分割見込書を申告期限までに提出すれば、後日、分割が整ったときに特例を適用し直すことができる
- 配偶者控除は分割成立後の更正・更正の請求で適用回復可能(相続税法第19条の2第6項)
- 小規模宅地特例は分割見込書が後から特例を適用し直すことができる主なルート。災害等の“やむを得ない事由”は補助的救済(租税特別措置法第69条の4第5項)
- 書面添付で「誠実な申告」として信頼を高められる
- 期限を守ることが、最も重要な税務リスク管理である
【法令・通達出典(2025/4/1改正準拠)】
- 相続税法第27条(申告期限)
- 相続税法第19条の2(配偶者の税額軽減)
- 租税特別措置法第69条の4(小規模宅地等の特例)
- 相続税法・租税特別措置法の調査・照会規定および施行規則様式(情報把握根拠)
- 相続税基本通達(分割見込書・やむを得ない事由の承認に関する規定)
- 税理士法第33条の2(書面添付制度)