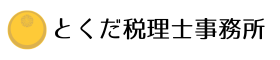面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
善意のつもりが贈与税対象に?親や祖父母が払う保険料の落とし穴
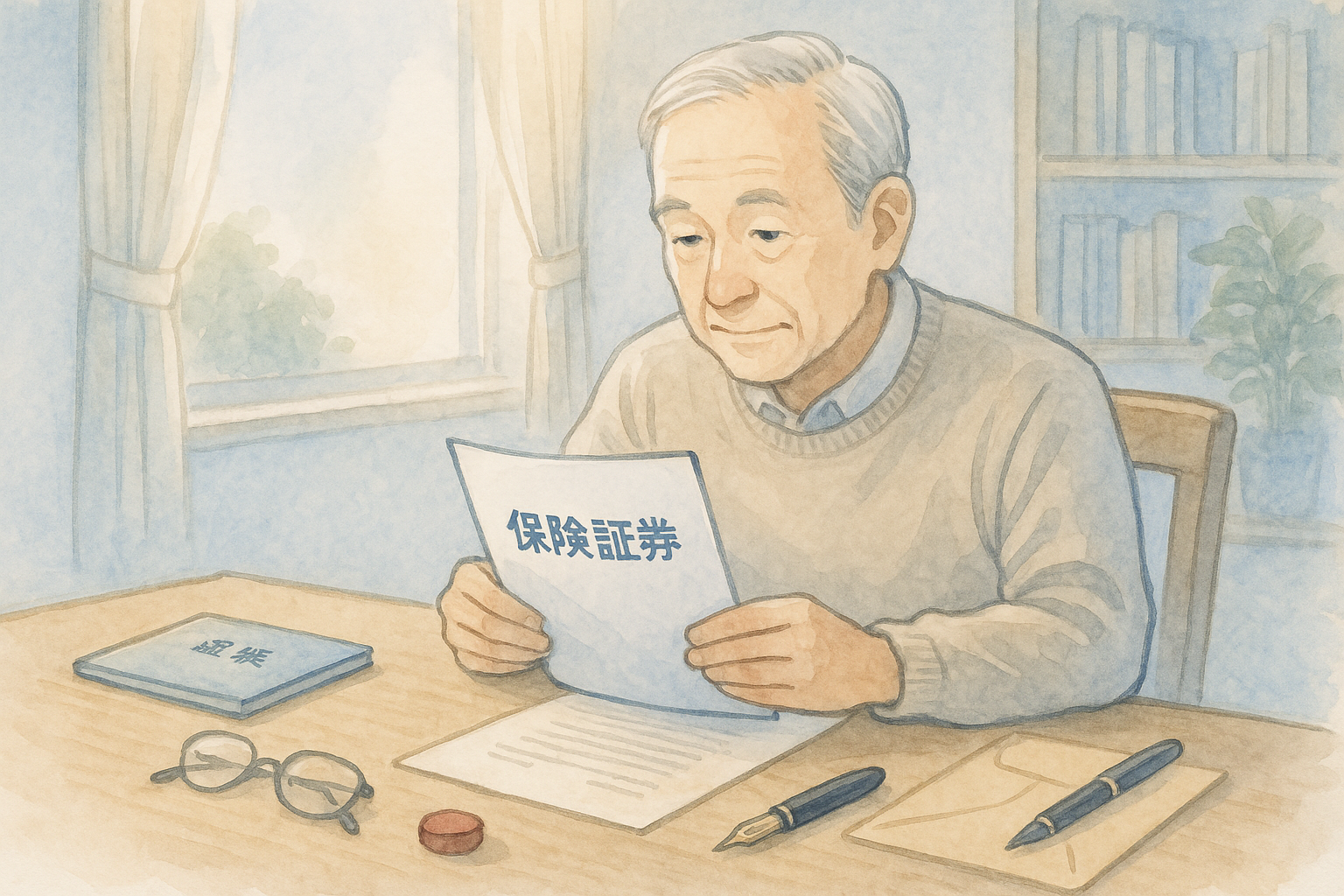
親や祖父母が、子や孫のために生命保険を契約してくれるのは珍しいことではありません。
「教育資金を少しでも助けてあげたい」「将来の安心を作ってあげたい」――その気持ちは、どの家庭でも自然なものです。
しかし、税務の世界では「誰が支払ったか」という事実が、想像以上に重要です。
契約者の名義よりも、実際に保険料を負担している人が誰か。
この一点を誤ると、意図せず贈与税の対象となる場合があります。
名義よりも「実質」が重視される
生命保険では、契約者・被保険者・受取人の三者関係で課税関係が決まります。
税務上は、「契約者の名義」よりも保険料を実際に負担している人(経済的負担者)が誰か、が最も重視されます。
契約者が子であっても、保険料が継続的に親の口座から支払われている場合、
税務署は「実質的には親が保険契約を所有している」と判断することがあります。
いわゆる名義保険(形式と実質の乖離)と呼ばれる状態です。

子どもの名義で契約してるから大丈夫だと思っていました。
保険料支払の口座だけ親のを使ってました……。



契約者の名義よりも、実際にお金を出している人が誰か、が重視されます。
名義が子でも、実質の保険料が親負担なら“名義保険”と判断される可能性がありますね。
保険料支払時点では贈与税は課されない
親や祖父母が保険料を払っているからといって、支払時点で贈与税が課されるわけではありません。
その時点では、まだ受取人に「確定した財産権」が移っていないからです。
贈与が成立するのは、保険金や年金受給権が確定した時点です。
つまり、課税のタイミングは以下のようになります。
| 受取形態 | 贈与が成立する時点 |
|---|---|
| 一時金 | 保険金を受け取った時点 |
| 年金形式 | 年金受給権が確定した時点(支給開始時) |
※年金受給権は支給開始時に評価されます(財産評価基本通達9-1~9-4)。
受取が一時金か年金かで課税タイミングが変わる
一時金で受け取る場合
親が保険料を負担し、子が保険金を一括で受け取ると、その受取時点で贈与税が課される可能性があります。
たとえば祖母が孫名義の学資保険を契約し、満期時に400万円を受け取った場合、
課税価格は「400万円 − 110万円(基礎控除)」=290万円となります。
年金形式で受け取る場合
年金形式で受け取る場合、贈与は「年金受給権が確定した時点」で一括成立します。
たとえば、保険会社が算出した年金受給権評価額が800万円であれば、その年に800万円を贈与として課税判定します。



年金で少しずつ受け取るなら、贈与税も少しずつかかると思っていました。



実際は違うんです。年金の支給が始まる時点で、“年金受給権全体”を贈与されたとみなされるんですよ。
たとえば、10年間で総額1,000万円受け取る契約なら、その1,000万円の現在価値が一度に贈与された扱いになります。
分割で受け取っていても、贈与税は“まとめて1回分”として課税されるため、金額が大きくなりやすいのです。
年金型の保険は見た目が少額でも、受給総額が数百万円〜数千万円になるケースも珍しくありません。
贈与税率は累進(最大55%)なので、想定以上の負担になるおそれがあります。
保険料相当額を贈与して本人が支払う場合
親や祖父母が直接保険料を払うのではなく、保険料にあたる金額を子や孫に贈与し、本人が自分で保険料を支払う方法もあります。
この場合、贈与税の課税時期はそのお金を受け取った時点です。
| ケース | 贈与が成立するタイミング |
|---|---|
| 親が直接保険料を払う | 保険金受取時または年金受給権確定時 |
| 親が保険料分を贈与し、子が自分で払う | 贈与を受けた時点 |
たとえば、親が毎年30万円を子に振り込み、子自身が保険料を払う場合、
その30万円がその年の贈与として確定します。
この方法を取ると、課税時期が明確になり、将来の贈与税リスクを回避しやすくなります。
(参考:タックスアンサーNo.4402・4408)
保険料を“もらって自分で払う”ときの贈与制度の選び方
この方法をとる場合、贈与の仕方によって使える制度や課税のタイミングが異なります。
代表的な制度には次の3つがあります。
① 暦年課税(通常の贈与)
- 毎年110万円までの贈与は非課税(相続税法第21条の5)。
- 110万円を超える部分のみ贈与税の対象。
- 毎年一定額を渡して保険料を支払う場合に向いています。
例:
毎年30万円の保険料相当額を贈与 → 課税なし。
10年間続けても合計300万円の贈与が「課税されない範囲内」で完結。
② 相続時精算課税
- 贈与者が60歳以上の親・祖父母、受贈者が18歳以上の子・孫なら選択可。
- 2,500万円の特別控除と、毎年110万円の基礎控除は別枠で併用可能です。
- → 各年の贈与額からまず110万円を控除し、残額がある場合は特別控除(2,500万円)を順次充当します。
- これにより、大口贈与でも贈与税の負担を抑えつつ、一括贈与が可能です。
その年に300万円を贈与した場合、
300万円 − 110万円(基礎控除)=190万円
→ 残190万円は特別控除2,500万円の枠内で処理(累計控除残が2,310万円に減少)。
この方式は、保険料原資を一括で贈与する場合や、一時払い終身保険を契約する場合に有効です。
ただし、一度選択すると暦年課税へは戻れません。
③ 障害者への贈与(特定贈与信託)
- 障害者を受益者とする信託契約を結び、条件を満たせば非課税となります
- 特別障害者は6,000万円まで、その他の特定障害者は3,000万円までが上限。
- 信託銀行や保険会社を受託者として、生活費・医療費に充てる信託を設計可能。
- 適用には税務署への「障害者非課税信託申告書」の提出が必要です。
本制度は生命保険とは異なる「信託契約」ですが、将来の生活・医療費を安定的に支えたいという親の願いを制度化するという点で、保険と同じ役割を果たすことができます。特に、名義保険や実質負担者問題といった保険制度の“落とし穴”を回避できる可能性がある点で、ここに取り上げています。
📘関連記事
障害のある子に安心して財産を残す方法|特定贈与信託で贈与税が非課税に



保険料を払ってもらうのではなく、保険料にあたる金額を贈与してもらって自分で払う方法もあるんですね



はい、そういう方法もあります。
その場合は、贈与の時期や金額が明確になり、暦年課税・相続時精算課税・障害者特例など目的に合わせて制度を選ぶことができます。
保険料贈与の方式比較表
| 方式 | 非課税枠 | 相続時への影響 (相続財産への加算リスク) | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 暦年課税 | 毎年110万円まで | 加算リスクあり | 年払い保険料など少額贈与 |
| 相続時精算課税 | 2,500万円(特別控除)+毎年110万円(基礎控除) | 基礎控除までは加算リスクなし、基礎控除を超える部分は必ず加算 | 一時払い保険・一括贈与 |
| 特定贈与信託(障害者) | 特別障害者:6,000万円/特定障害者:3,000万円 | 加算リスクなし | 障害者の長期生活支援 |
💡親や祖父母が払ってくれた保険料が問題になるタイミング
相続のときに発覚しやすい
相続税の調査では、税務署が必要に応じて、銀行や生命保険会社に対し取引内容や契約情報の照会を行います。
銀行や保険会社は照会を受けると回答義務があります。
そのため、被相続人(親や祖父母)の口座から保険料が引き落とされていた場合、
その契約が子や孫名義であっても、照会によってすぐに確認され、
「実質的には親が保険料を負担していた」と判断されることがあります。
たとえば――
- 学資保険や終身保険の引き落としが、被相続人名義の口座で続いていた
- 契約者や受取人が子や孫になっている
こうしたケースでは、「過去の贈与があった」として贈与税の申告漏れを指摘されることがあります。
さらに、過去にさかのぼって修正が必要になる場合、
延滞税や無申告加算税が課され、
追徴税額が本税より重くなることも珍しくありません。
調査では、保険料の出金記録・契約書・引き落とし口座などが照合され、
「誰が実際に負担していたか」を詳細に確認されます。
つまり、契約書の名義だけでなく、資金の流れそのものがチェックされるのです。



相続のときに“保険の名義”をきっかけに調査が始まることがあります。
名義は子や孫でも、保険料が親の口座から引き落とされていれば、
実質的な負担者は親と判断される可能性が高いんです。
まとめ:思いやりの設計を“制度で守る”
保険は「家族の思いやり」を形にする制度ですが、
税務上はお金の流れの実質がすべてです。
契約者の名義よりも、保険料を誰が実際に負担したかが課税判断の核心になります。
支払時点では課税されなくても、受取時に贈与税が発生することがあります。
また、保険料を贈与して自分で払う設計にすれば、
課税の時期が明確になり、リスク管理もしやすくなります。
ただし、暦年課税・相続時精算課税・特定贈与信託など、
選ぶ制度によって非課税枠や将来の相続への影響は大きく変わります。
こうした違いを正確に見極めるには、
契約形態・支払経路・家族関係・相続の見通しを総合的に把握する必要があります。
“思いやりのつもりが課税トラブルになった”という事例は少なくありません。
契約前や名義変更前に税理士へ相談し、
思いをそのまま安心に変える制度設計をしておきましょう。
契約前・名義変更前に税理士へ相談し、安心できる制度設計をしておきましょう。
【参考・根拠資料】
- 相続税法第3条・第21条の3・第21条の5・第21条の9〔e-Gov|令和7年4月1日施行改正を反映〕
- 相続税法施行令第1条の2(生命保険契約等の範囲)
- 財産評価基本通達9-1~9-4(年金受給権の評価)
- タックスアンサーNo.4402/No.4408/No.4123/No.1620
- 国税庁「相続時精算課税のあらまし(令和6・7年改正反映)」
- 国税庁手続案内「B1-19 障害者非課税信託申告の手続」
- 東京国税不服審判所 平成27年3月24日裁決(学資保険)
- 国税通則法第60条・第66条(延滞税・無申告加算税)