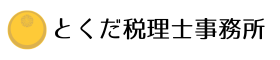面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
株式や投資信託で損が出たときの配当・利子の課税方法

はじめに
株式や投資信託への投資では、売却による損益に加えて、配当金や利子、分配金といった収入も発生します。多くの投資家が「損失が出たとき、配当や利子にかかる税金はどうなるのか?」という疑問を抱くのではないでしょうか。
実は、どの課税方法を選ぶかによって税額が大きく変わることがあります。この記事では、基本的な仕組みを分かりやすく解説します。
売却損と配当の損益通算

株を売って損失が出てしまいました。同じ年に配当金も受け取っているのですが、この損失と配当は相殺できるのでしょうか?



はい、条件を満たせば可能です。確定申告をすれば、売却損と上場株式等の配当(申告分離課税を選択したもの)や他の株式の譲渡益を損益通算できます。
👉 参考:
利子所得の扱い(債券や投資信託の場合)



株式以外に債券や投資信託も持っているのですが、利子収入も損失と相殺できますか?



利子所得は、その種類によって取り扱いが異なります。
株式そのものからは利子は発生しませんが、国債や社債などの債券投資、または債券を組み入れた投資信託を保有している場合には利子所得が関係してきます。
- 預貯金の利子:源泉分離課税で完結し、確定申告もできません。したがって売却損との通算は不可です。
- 特定公社債等(国債・地方債・公募公社債など)の利子:2016年以降は申告分離課税に一本化されており、確定申告で申告すれば売却損と通算できます。
👉 参考:



なるほど、株式だけなら利子は関係ないけど、投資信託や債券を持っていれば通算できる可能性があるんですね。
配当所得の扱い



株や投資信託からの配当や分配金はどうでしょうか?



上場株式等の配当には、3つの選択肢があります。
- 申告不要制度:源泉徴収で完結。ただし損益通算はできない。
- 総合課税:給与など他の所得と合算し、条件次第で配当控除を受けられる。
- 申告分離課税:株式の譲渡損と同じ区分で計算でき、損益通算が可能。
👉 参考:



売却損を活かすなら、申告分離課税を選ぶのが一般的です。ただし、総合課税で配当控除を使ったほうが有利になるケースもありますので、試算が欠かせません。
住民税・国保への影響



総合課税を選ぶと住民税や国民健康保険料が上がるって聞いたんですが…?



確かに影響することがあります。
以前は、所得税と住民税で異なる課税方式を選べたので、住民税だけ申告不要を選んで国保料を抑えることも可能でした。ところがこの制度は令和5年度(令和4年分申告)で終了しました。令和6年度以降は、所得税で選んだ課税方式がそのまま住民税にも適用される仕組みに変わっています。
👉 重要なポイント:
- 令和5年度(令和4年分申告)まで:所得税と住民税で別の課税方式を選択可能
- 令和6年度(令和5年分申告)から:所得税と住民税は同一方式が強制適用
- 現在は「住民税だけ申告不要を選ぶ」といった調整はできない
損失の繰越控除



株式や投資信託の売却損は、翌年以降3年間繰り越して、上場株式等の譲渡益や配当(申告分離課税を選択したもの)と相殺できます。ただし、連続して確定申告をすることが条件です。
👉 参考:
まとめ
株式や投資信託で損失が出た場合の配当や利子の取り扱いは、申告不要・総合課税・申告分離課税のいずれを選ぶかによって税額が大きく変わります。



やっぱり自分だけ判断するのは不安ですね…



適切な申告を行えば、不必要な税金を支払わずに済みますし、損失の繰越制度を活用することで将来の節税効果も期待できます。