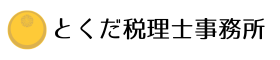面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
【2025年版】 生前贈与と相続税の最新ルール解説
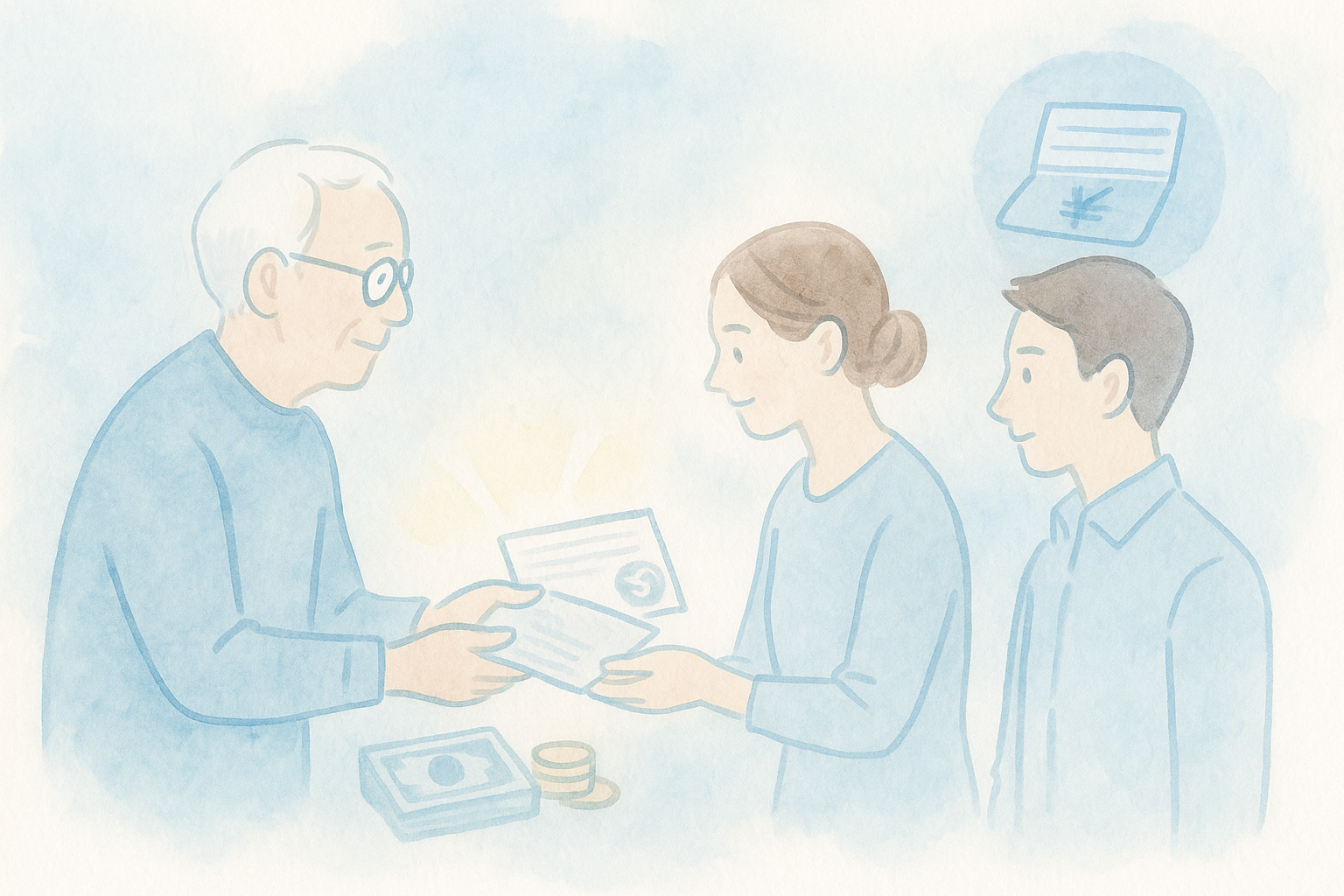
これまでは「毎年110万円までなら安心」と言われてきましたが、2024年(令和6年)の改正で状況は変わりました。
- 暦年課税では、相続開始前7年以内の贈与が加算対象となり、従来の「110万円までは相続税にも影響しない」という考え方は通用しなくなりました。小口でも相続のタイミング次第では加算されます。
- 一方で、相続時精算課税には新たに「年間110万円の基礎控除」が導入され、これまで煩雑だった少額贈与については、110万円までは申告不要で贈与できるようになりました。
つまり、同じ「110万円の贈与」でも、選ぶ制度によって相続への影響や実務負担が大きく異なる時代に入ったのです。
この記事では、改正ルールの全体像と実際の影響、そして実務上の注意点を整理します。
基本:贈与税の仕組み
贈与には2つの課税方式があります。
- 暦年課税
毎年110万円までは非課税。それを超える部分は累進課税。最も利用されている。 - 相続時精算課税
2,500万円まで非課税だが、超えた部分は20%課税。将来の相続で持ち戻し精算する仕組み。2024年(令和6年)の改正で「年間110万円の基礎控除」が導入され、110万円以下は申告不要に(2024年1月1日以後の贈与に限る)。

暦年課税と相続時精算課税って、結局どちらが得なんですか?



状況によります。少額を毎年コツコツ渡すなら暦年課税が基本ですが、改正で相続時精算課税でも110万円までは申告不要で贈与できるようになりました。
従来は「相続時精算課税=大きな資金移動に限る」というイメージでしたが、2024年改正で年110万円の基礎控除+申告不要が設けられたことで、少額でも相続時精算課税を利用してコツコツ贈与するという新しい選択肢が生まれています。
改正ポイント(2024年改正)
持ち戻し期間の延長と加算除外
相続開始前「3年以内の贈与」は、従来どおり全額が相続財産に加算されます。
2024年(令和6年)改正で、この期間が「7年以内」まで拡大されました。
ただし、延長された“3年超〜7年以内”の部分には救済規定があります。
相続時精算課税に基礎控除110万円を導入
従来は「非課税枠2,500万円」のみで、毎年の少額贈与でも申告が必要でした。改正後は、年間110万円まで非課税・申告不要になり、使い勝手が大幅に改善しました(2024年1月1日以後の贈与に限る)。
段階適用のスケジュール
改正後の7年ルールは、一気にフル適用されるわけではなく、段階的に広がります。
- 2024年(令和6年)〜2026年(令和8年)の相続
従来どおり「3年以内」の贈与のみ加算対象。 - 2027年(令和9年)1月1日〜2030年(令和12年)12月31日の相続
「2024年(令和6年)1月1日以後の贈与」が加算対象。
ただし、この期間に該当する“3年超”部分については総額100万円まで加算除外。 - 2031年(令和13年)1月1日以後の相続
「相続開始前7年以内の贈与」が加算対象(フル7年ルール)。
ケース別シミュレーション
Case 1:2024年(令和6年)末に相続が発生
父が2024年6月に子へ500万円を贈与、同年12月に亡くなった場合。
→ この時期は従来どおり「3年以内のみ」加算。結果は旧制度と同じ。
Case 2:2027年(令和9年)に相続が発生
父が2024年に500万円、2025年に500万円を贈与し、2027年に死亡。
→ 2024年・2025年分とも加算対象。
→ ただし、この時期は「3年超部分の合計から総額100万円除外」が認められる。



なるほど、“各年110万円”ではなく“合計100万円”なんですね。



はい。しかも実際に適用されるのは2027年(令和9年)以降の相続から、という点が重要です。
Case 3:2028年(令和10年)に相続が発生
父が2024年に500万円を贈与し、2028年に死亡。
→ 2024年分は加算対象。ただし“3年超”なので、500万円−100万円=400万円が加算額。
Case 4:相続時精算課税を利用
父が2024年に子へ300万円を贈与。
→ 110万円は基礎控除で非課税・申告不要。残り190万円のみ申告。
→ 相続時には、この190万円が持ち戻し対象となる。
実務で注意すべきポイント
- 贈与契約書の作成
贈与契約書には法律上の作成義務はありません。しかし、当事者間で作成・保管しておくことで、贈与の事実(当事者の意思表示+履行)を明確にでき、『名義預金』と判断されるリスクを抑えることができます。 - お金の流れを明確に
贈与は、現金を手渡しするよりも振込で記録を残すことが重要です。通帳に「贈与金」などとメモを残すことで、資金の性質が明確になります。
注意すべきは「名義預金」です。これは、通帳や名義は子のものになっていても、実際には親が管理・入出金をしている状態を指します。名義預金と判断されると、形式上は贈与していても実質的には親の財産とみなされ、相続時に課税対象に戻されてしまいます。
→ ポイントは、贈与したお金を受贈者自身が自由に管理・使用できる状態にしておくことです。 - 高齢の親からの贈与
2024年(令和6年)の改正で加算期間が7年に延長されたため、親が高齢になってからの贈与は、相続開始までの期間が短いほど相続財産に戻されやすくなりました。例えば、80歳の親が子に贈与をしても、5年以内に亡くなればその贈与は相続財産に加算されてしまいます。 - 相続時精算課税の選択
2024年(令和6年)の改正で基礎控除110万円が新設され、使い勝手は大きく改善しました。ただし、一度選ぶと暦年課税に戻れないため、安易な選択は禁物です。
- 住宅購入や教育資金など、まとまった金額を一気に移したい場合
- 収益不動産を早めに次世代に移管し、相続財産として増加するのを防ぎたい場合
- 将来的に相続税申告が不要と見込まれる家庭で、安心して毎年110万円を贈与したい場合
- 将来の値上がりが見込まれる資産を早めに移しておきたい場合(贈与時点の価額で持ち戻されるため、値上がり益を相続財産から切り離せる)。
⚠️相続時精算課税のリスク
相続時精算課税は、基礎控除110万円の新設で使いやすくなった一方、いくつかのリスクもあります。
- 一度選ぶと暦年課税には戻れない
- 相続税そのものが減るわけではない
- 値上がり資産を贈与後に売却すると子に大きな所得税がかかる可能性
- 将来の財産状況や制度改正次第で不利になることもある



今後も制度改正次第で有利・不利が変わる可能性があるため、「将来の財産規模や制度変更を踏まえた柔軟なシミュレーション」が不可欠です。
まとめと展望
- 暦年贈与の加算は段階的に7年へ拡大。
- 2027年(令和9年)以降の相続では、“3年超〜7年以内”部分に総額100万円の加算除外が導入。
- 相続時精算課税には110万円基礎控除(2024年以降の贈与)が新設され、基礎控除後の残額のみ持ち戻し。
7年ルールは2031年(令和13年)以後にフル適用されます。現在は段階的な移行期。
贈与契約書の作成、通帳の管理、そしてどの制度を選ぶかの見極めがカギとなります。
今後も「相続と贈与の一体課税」への移行が議論されており、さらに制度が変わる可能性があります。2025年(令和7年)の今は、「知らなかった」で損をしないために、早めに専門家へ相談することが重要です。



結局、自分の家の場合はどうするのが一番いいんでしょうか?



財産規模や家族構成で有利不利が全く変わります。一般論で判断せず、早めに税理士に相談してシミュレーションしてみましょう。