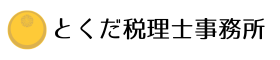面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
税務署に否認されない!家族間のお金のやり取りと相続税の最新注意点
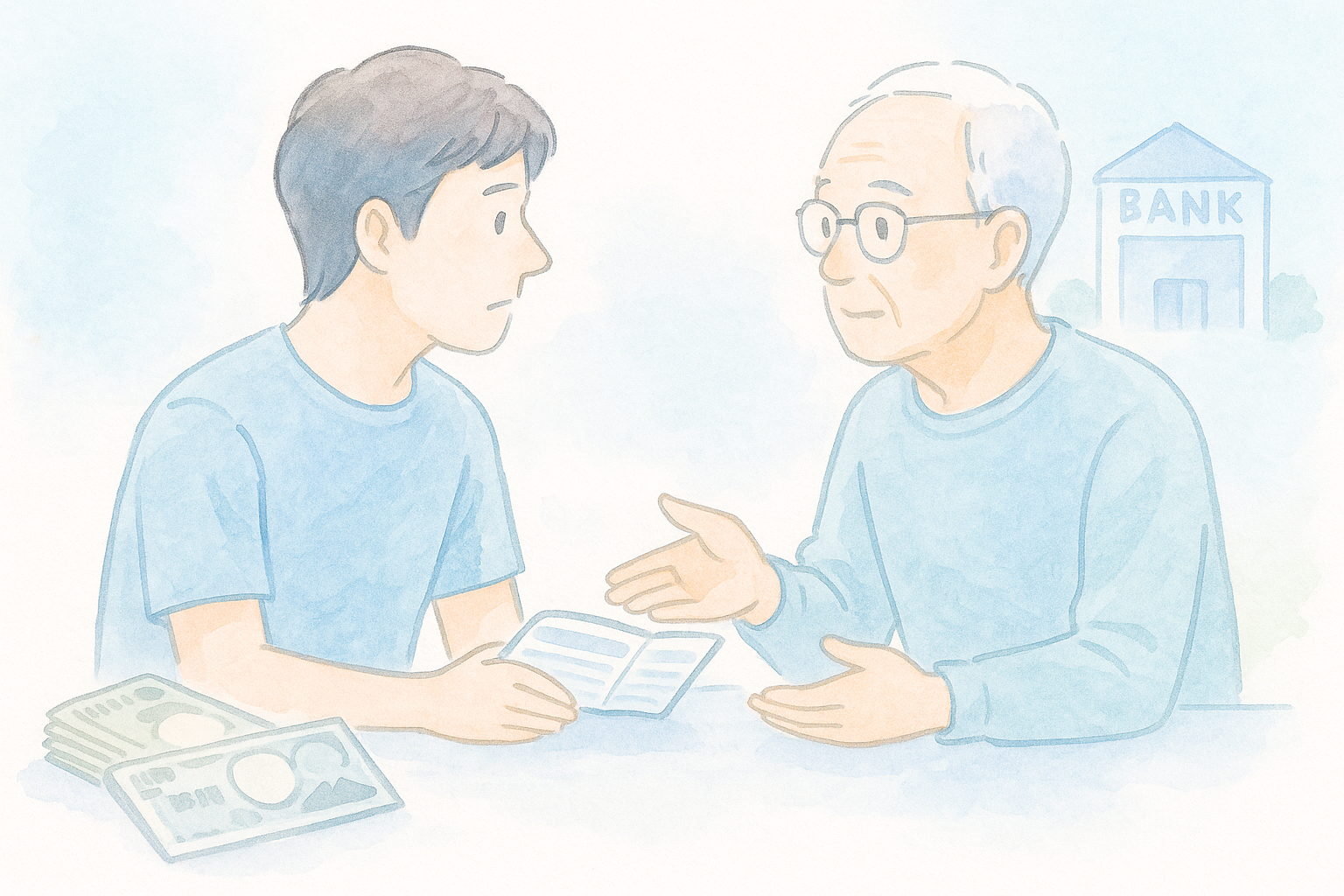
親が子に仕送りをする、夫婦でお金を融通し合う、祖父母が孫に学費を渡す。
どこの家庭でも普通に行われていることです。
「ちょっと助けてあげただけ」「名義を変えておいただけ」――そんな感覚で済ませてしまうのが家族間のお金のやり取りの特徴です。
しかし税務署は感情では判断しません。
家族だから特別扱いされることはなく、形式や証拠がなければ“贈与”や“名義預金”と認定されるリスクがあります。

相続税調査で最も多く指摘されるのは“名義預金”。つまり家族間のお金のやり取りなんです。曖昧にしておくと後で大きな問題につながります。
贈与と認められないと「名義預金」にされる
贈与は「あげる」「もらう」という意思表示と実際の受け渡しで成立しますが、税務署に認められるには契約と履行の証拠が必要です。
- 贈与契約書がない
- 贈与税の申告をしていない
- 受贈者(子や配偶者)が自由に管理・使用していない
こうした点があると、税務署は「贈与の実態が薄い」と疑います。
父が毎年100万円を子の口座に振り込み続けていました。父は「贈与しているつもり」でしたが、契約書も申告もなく、子は全くそのお金を使っていません。
→ 税務調査では「父の財産」と判断され、相続財産に加算。申告漏れとして追徴課税を受けました。



名義預金かどうかは、出資者・管理権限・利息の帰属などを総合的に見て判断されます。単に“名義が子”というだけでは通用しないのです。
生活費や教育費は非課税だが条件あり
ここで重要なのは、扶養義務者間での生活費・教育費は非課税という点です。これは「相続税法(贈与税関係)第21条の3第1項2号」に定められています。
ただし条件があります。「生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てる」場合に限るのです。まとめ渡しや余剰の貯蓄は課税になるリスクがあります。



じゃあ大学生の子に仕送りしたり、学費を払ったりするのは贈与じゃないんですか?



はい。通常必要と認められる範囲であれば非課税です。ただし“必要な都度・直接充てる”ことが条件です。
例えば、
- 大学生の子に、毎月家賃として8万円を振込、学費として大学に直接200万円を納付 → 非課税(要件充足)
- 年初に300万円をまとめて渡し、そのうち余った分を子が貯金 → 貯金部分は贈与と認定され課税リスク(「都度・直接」の要件を満たさない)
結婚に関するお金:祝儀とまとまった援助は扱いが違う
ここは誤解が多いポイントなので、整理して明確に書きます。
A)一般的な結婚祝い(ご祝儀や祝物)
個人から受ける香典・祝物・見舞いなど、社会通念上相当と認められる金品は、贈与税がかかりません(申告不要)。結婚祝いのご祝儀もこの範囲に含まれます。
B)まとまった結婚関連資金の援助(挙式費、新居費などの実費負担)
これは原則として課税対象です。ただし、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」を利用すれば、結婚関係費用については最大300万円まで非課税とすることが可能です。
- 適用期限:2027年3月31日まで延長(令和7年度税制改正)
- 所得制限:前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は対象外
- 手続:金融機関経由で専用口座を開設し、領収書で使途管理が必要



じゃあ“ご祝儀”は普通の額なら申告不要。でも、親からの挙式費や新居費の大きな援助は、特例を使わないと課税になるんですね?



そのとおりです。少額の祝儀と、まとまった資金援助は税務上の扱いが別物。制度の使い分けが重要です。
「貸したつもり」は通用しない
親が子に「返してくれればいいから」とお金を渡すことはよくあります。
しかし契約書がなく返済もなければ、それは貸付ではなく贈与と判断されます。
母が息子に500万円を渡し、「返してね」と口頭で伝えただけ。返済も利息もなし。
→ 税務署は「実質は贈与」と判断し、贈与税の課税対象に。



貸付と認められるためには、返済実績と利息の授受が必要です。
契約書がなくても状況次第で判断されることはありますが、形式を整えておかないと『贈与』と見なされやすいのです。
さらに、実務上は以下の要素がポイントになります。
- 返済:定期的に返済が行われていること(銀行振込など証拠が残る方法が望ましい)
- 利息:市中金利を基準とした相当利率(例:年1~2%程度)を設定し、実際に支払うこと
- 契約書:金銭消費貸借契約書を作成し、金額・利率・返済期限・遅延損害金などを明記。確定日付を取れば証拠力が高まる



契約書がなくても返済と利息がきちんと行われていれば貸付と認められる可能性はあります。
証拠が不十分だと贈与認定リスクが高くなります。返済・利息・契約書の3点セットで備えておくのが確実です。
相続税の実務にどう響くか
名義預金や曖昧な資金移動は、相続税の実務で特に問題になります。
- 相続財産に加算され、申告漏れとされる
- 重加算税や延滞税が課される可能性
- 遺産分割協議で「誰の財産か」をめぐって争いになる
母名義の口座に1,000万円。実際は母が認知症で使えず、長男が自由に出し入れしていました。
→ 相続開始後、長男は「自分のお金」と主張しましたが、税務署は「母の財産」と判断し相続財産に加算。申告漏れ扱いとなり、重加算税まで課されました。



税務署は資金の出所・管理・利息の帰属を見て、総合的に判断します。“名義が誰か”ではなく“実質的に誰のものか”で決まるのです。
贈与・貸付でもリスクはある
相続税だけでなく、生前の資金移動自体にもリスクがあります。
- 贈与税の申告漏れ
住宅取得資金援助や結婚・子育て資金援助は、それぞれの非課税制度を要件どおりに使わないと課税。 - 貸付と所得税
利息を設定すれば雑所得として課税。設定しなければ贈与認定リスク。



つまり“相続のとき”だけでなく、“贈与や貸付の段階”でも課税リスクがあります。家族間だからと安心せず、すべて整理しておくことが大切です。
予防策と実務的な対処法
- 贈与
贈与契約書を作り、確定日付や公正証書で証拠力を高め、贈与税申告で裏付けを残す。 - 貸付
金銭消費貸借契約書を作り、返済スケジュールや利息を明記し、返済を実行。証拠を残す。 - 名義預金
そのまま放置せず、正式に贈与するか、本人名義に戻す。 - 生活費・教育費
「必要な都度・直接」以外の渡し方(まとめ渡し・貯金化)は避ける。
家族間のお金は曖昧になりやすいですが、書面と記録を残すことで、後のトラブルや税務リスクを避けられます。
まとめ
日本は急速に高齢化が進み、親から子、祖父母から孫へと資産を移すケースが増えています。
同時に、国は相続と贈与の一体的把握を進めており、2024年改正では「相続前7年以内の贈与加算」や「相続時精算課税の110万円基礎控除新設」が導入されました。2025年度改正では結婚・子育て資金非課税の延長(2027年3月31日まで)や物納制度の見直しなどが行われています。



暦年贈与なら毎年110万円まで非課税だから安心、と思っていましたが、そうでもないんですね。



2024年の改正で、相続前7年以内の贈与は相続財産に加算されることになりました。これまで3年だったのが大幅に延長されたんです。
“毎年110万円をコツコツ贈与すれば完全に相続税対策になる”という考え方は通用しにくくなっています。制度の変化を踏まえて計画を立てることが必要です。
制度は複雑化し、税務署のチェックも厳しくなっていますから、これからの時代には、“相続に備える”だけでなく“家族間の資金移動全般を安心して行う仕組み”を整えることが必要です。
当事務所では、生前贈与のプランニング、名義預金の整理、相続税申告まで一貫してサポートしています。専門家の確認が安心につながります。