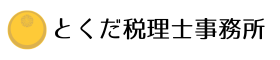面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
故人に借金があるか分からないときの調べ方と相続税の影響
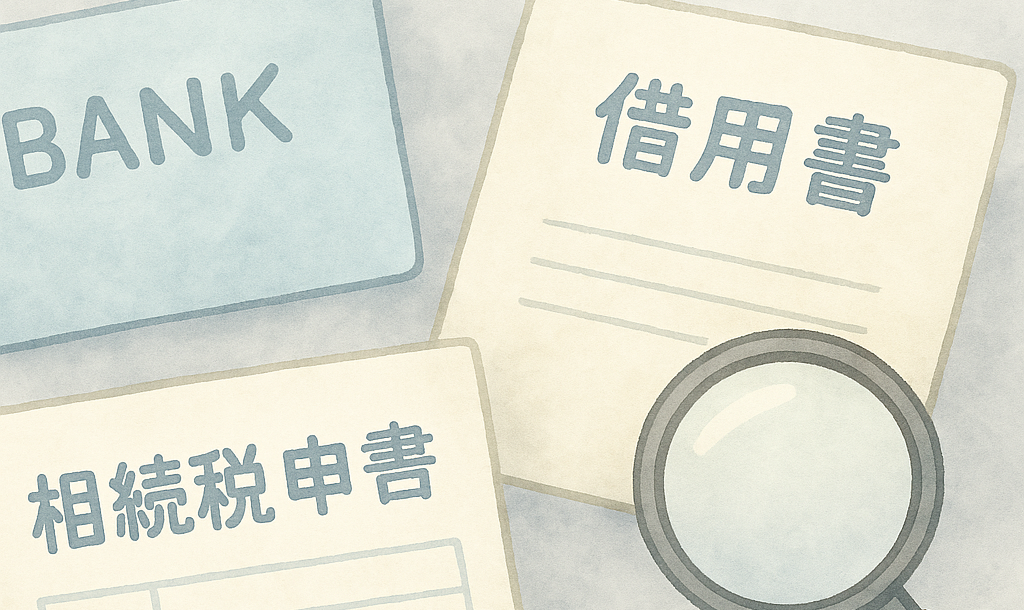
家族が亡くなったあと、「借金があったのではないか」と不安になる方は少なくありません。住宅ローン、カードローン、さらには連帯保証など、確認しないと分からない負債が潜んでいることもあります。
借金の有無は、相続放棄や限定承認といった相続手続きの選択だけでなく、相続税の申告にも直結します。

父に借金があるか分からないんですが、税金の手続きにも関係しますか?



はい。借金は相続税の計算で“債務控除”できますし、放棄を選んだ場合には申告義務自体がなくなるケースもあります。ただし保証債務のように扱いが難しいものもあるんです。
本記事では、借金の調べ方から、相続税との関係、注意点まで税理士の視点で解説します。
借金の調査方法
1. 書類・通帳の確認
- 銀行やカード会社からの督促状
- ローン契約書・保証書
- 通帳の定期引落し記録



通帳に“カードローン返済”と毎月出てました。借金ですよね?



返済履歴の可能性が高いですね。契約内容を確認しましょう。
2. 電話履歴・郵便物のチェック
金融機関からの着信、未開封の請求書も手がかりになります。
3. 信用情報機関での調査
客観的に調べるには、信用情報機関での開示請求が有効です。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):クレジットカード、信販、携帯端末割賦など(死亡者開示の郵送手続の案内あり)
- JICC(日本信用情報機構):消費者金融、カードローン(法定相続人や二親等以内の血族による郵送申込が可能)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行・信用金庫のローン(住宅ローン、自動車ローン等)。処理期間の目安は7〜10日ほど(FAQ記載)。



亡くなった人の借金の情報が開示できるんですか?



はい。相続人であれば可能です。戸籍や住民票除票で“相続人であること”を証明すれば請求できます。
開示請求の流れ
- 各機関のHPから申請書を取得
- 提出書類:
- 相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 故人の住民票除票または死亡診断書コピー
- 相続人本人の身分証明書
- 手数料(定額小為替など)を添えて郵送
KSCはFAQで「7〜10日程度」と案内(時期により変動)。
開示で分かる内容
- 借入残高
- 返済状況(延滞の有無など)
- 契約の有無(保証人契約の表示可否は登録範囲に依存)
※登録範囲は機関ごとに異なります(CIC=クレジット・信販、JICC=消費者金融、KSC=銀行系)。
ただし、知人間の借金や未加盟業者のローンまでは分かりません。
借金が判明した場合の選択肢
1. 相続放棄
借金が多いときは、家庭裁判所に相続放棄を申述すれば借金も財産も承継しません。
- 期限:相続開始を知った日から原則3か月以内(民法915条)。起算点や家庭裁判所の伸長許可により例外もあり得ます。
- 効果:借金の返済義務なし



借金があると分かったらすぐ放棄した方がいいんですか?



原則は3か月以内に決める必要があります。迷っている場合は早急に専門家へ確認してください。放棄すると税務上も“相続人でなかった”扱いになるため、その人は相続税申告義務もなくなります。
2. 限定承認(詳しく解説)
限定承認とは「相続によって得た財産の範囲でのみ借金を返す」とする制度です。
- 財産 > 借金 → 差額を取得
- 財産 < 借金 → 財産の限度で返済し、それ以上は負担しない



放棄だと全部捨てることになるけど、限定承認ならプラスだけ残せるってことですか?



そうです。ただし相続人全員で合意して申述しなければ成立しません。
メリット
- プラス財産を残せる(不動産や事業資産がある場合に有効)
- 借金が財産を上回っても超過分は免責
- 負債額が不明なときの“安全弁”
デメリット(実務上のハードル)
- 相続人全員の同意が必須(1人でも反対で不可)
- 家庭裁判所への申述、財産目録作成、公示公告、債権者通知など手続きが煩雑
- 実務での利用は少なく、関係機関も慣れていない場合がある



どうしてあまり使われないんですか?



放棄の方がシンプルで早いからです。限定承認は制度上は便利ですが、実務では“手間とリスク”が大きく、例外的にのみ選ばれます。
税務上の論点
限定承認は相続税だけでなく、所得税にも影響します。
- 相続税:純財産額に基づいて課税価格を計算(放棄・単純承認と同じ枠組み)。
- 所得税:所得税法59条により「みなし譲渡課税」の対象。換価して借金を返済する場合、時価で譲渡したとみなされ譲渡所得課税が発生。準確定申告が必要になることもあります。



限定承認なら税金は心配いらない?



逆です。税務処理はむしろ複雑になります。不動産がある場合などは、譲渡課税の影響を必ず確認してください。
3. 債務整理
放棄や限定承認が難しい場合は、弁護士による債務整理を検討します。
税理士目線での重要ポイント
債務控除の範囲
相続税では、相続開始時に存在する「確実な債務」のみ控除できます。保証や連帯関係の取扱いに注意。
- 通常の借入金や未払い税金:控除可
- 保証債務:原則控除不可。ただし主債務者が弁済不能で、保証人が履行せざるを得ず求償不能な部分は控除可(相基通14-3)。
- 連帯債務(共同借入):各自の負担部分が明らかな限り控除可(相基通14-3)。



父が友人の保証人でした。この保証債務は控除できますか?



原則は不可です。ただし主債務者が返せない状況で、かつあなたが求償できない部分は例外的に控除できます。
申告要否の判断(“三分け”)
- 課税価格(=財産-債務)が基礎控除以下なら申告不要
- 課税価格が基礎控除超なら申告が必要
- 小規模宅地や配偶者の税額軽減などの特例で税額ゼロにする場合は申告が必要(税額ゼロでも要申告)



借金があるから申告はしなくてもいいのかしら?



そう単純ではありません。財産から債務を引いた課税価格が基礎控除を超えていれば申告が必要です。借金があっても、プラスが残れば要申告です。
申告期限と熟慮期間の関係
- 相続税の申告期限は**「相続開始を知った日の翌日から10か月」。
- 相続放棄の熟慮期間(原則3か月)は民法上の概念で、税務上の期限は延びません。並行管理が必要。
注意点
- 借金の一部を返済すると、民法921条に基づき「単純承認」と評価され得る(相続放棄できなくなるおそれ)。個別事情で判断は分かれるため、返済行為は控えるのが安全。
- 相続放棄は原則3か月以内。起算点や家庭裁判所の伸長許可の余地はあるものの、迷う場合は早めの確認が不可欠。
- 連帯保証債務は税務上控除不可が原則。連帯債務(共同借入)とは別物である点に注意(相基通14-3)。



取り立ての電話が来たら、お金を払ってしまいそうで…



それは危険です!返済してしまうと“相続を承認した”と判断される可能性があります。まずは相続放棄の可否を確認しましょう。
事例紹介
ケース1:相続放棄で救われた例
あるご家庭では、亡くなった父親の遺品整理をしていたところ、督促状が数通見つかりました。さらにCICへの照会を行った結果、消費者金融から複数の借入があることが判明しました。
最初は「父の財産を引き継がないのは申し訳ない」と迷いがありましたが、確認すると残された財産はわずかで、とても借金を返済できる状況ではありませんでした。
税理士が関与したポイント
- 信用情報の開示結果を整理して「確実な債務」であることを確認
- 相続放棄を選択すれば借金返済義務を負わないことを丁寧に説明
- 家庭裁判所への相続放棄申述をサポート
結果として、相続人は3か月以内に相続放棄の手続きを終え、借金を引き継がずに済みました。税務面でも「放棄した人は最初から相続人でなかった扱い」になるため、申告義務もなくなりました。
ケース2:限定承認を選んだ例
別のケースでは、母親が亡くなったあとに判明したのは、自宅不動産と多額の住宅ローンでした。ローン残高は不動産の評価額とほぼ同額で、単純に相続放棄すると住んでいた家を失うリスクがありました。
そこで相続人全員(子ども2人)が話し合い、限定承認を選択しました。
税理士が関与したポイント
- 財産目録の作成を支援し、家庭裁判所への限定承認申述をサポート
- 債権者への公告や通知など、複雑な手続きを専門家と連携して進めた
- 不動産を売却してローン返済を行う際の「みなし譲渡課税」をシミュレーションし、準確定申告を適切に行った
結果的に、不動産は処分されましたが、借金返済後にわずかに残った資産を子どもたちが受け取ることができました。さらに税務面でも、課税関係を整理して適正に申告できたことで、後日のトラブルを回避できました。
専門家に相談するメリット
相続の現場では、法的判断(放棄・限定承認・承認)、税務判断(債務控除・申告要否・みなし譲渡課税)、実務対応(期限管理・連絡調整)が同時並行で走ります。独力で進めると、「期限を過ぎた」「証拠が足りない」「手続きが噛み合わない」といった躓きが起きやすいのが実情です。そこで税理士が入ると、次のようなサポートが期待できます。



何から手をつければ良いか分からなくて…。



“いま必要な確認”と“いつまでに決めるか”を一緒に設計します。手戻りを減らしましょう。
- 信用情報の開示サポート
相続人要件・必要書類・申請手順の整備、結果の読み解きまで伴走。債務の網羅性・確実性を確認して債務控除の裏付けを固めます。 - 債務控除の可否判断(保証・連帯の線引き)
連帯債務は負担部分の控除、連帯保証は原則不可など、実務で混同しやすい点を一次資料に沿って判定します。 - 申告要否とタイムライン設計
3か月(熟慮)と10か月(申告)は別時計。放棄/限定承認の見極めと並走する申告準備を両建てで進めます。 - 限定承認を選ぶ場合の実務・税務のハンドリング
財産目録、公示・債権者通知、換価とみなし譲渡課税のシミュレーション、準確定申告まで一気通貫で支援。 - 裁判所・金融機関・他士業との連携のハブ
弁護士・司法書士・不動産業者等と連動し、連絡・書式・スケジュールの一本化で手戻りを抑えます。 - 証拠・書類の整備
残高証明、契約関係、開示結果の突合せなど、税務署に通る形でドキュメントを整理します。



自分でやるより早く、漏れなく進みそうですね。



判断の材料を“揃える・可視化する”のが私たちの役割です。ゴールから逆算して、最短ルートで進めましょう。
相続は“時間勝負”の側面があります。迷いがある段階でこそ専門家に相談することで、選択肢の幅が広いうちに最適解へ辿り着けます。
まとめ
相続において借金の有無を確認することは、単に「負の遺産を引き継ぐかどうか」を決める作業ではありません。法律的な選択と、税務的な義務の双方に直結する重要なステップです。
実務では、多くの家庭が「相続放棄」か「単純承認」を選びます。限定承認は制度として残されているものの、相続人全員の同意や煩雑な手続きが必要なため、利用されるケースは多くありません。それでも「不動産や事業を残したいが借金も多い」という特殊な状況では、有効な手段となり得ます。
税務の面では、借金は相続税計算で差し引ける(債務控除)ため、税額を左右する大きな要素になります。ただし保証債務など一部は控除が認められない場合もあり、専門的な判断が欠かせません。さらに、相続放棄の熟慮期間(3か月)と相続税申告期限(10か月)は別物であり、申告準備は並行して進める必要があります。
借金があるかどうかの確認は
- 法的な判断(放棄・限定承認・承認のいずれを選ぶか)
- 税務的な判断(債務控除の適否、譲渡課税の有無、申告義務の有無)
- 実務的な対応(相続人間の話し合い、手続きの複雑さ、期限管理)
を正しく進めるための基盤になります。
借金の有無を把握することは、相続人を守るための防御であり、税務を適正に処理するための前提条件でもあります。どの選択肢を取るにしても、必要なのは「正確な情報に基づいた判断」です。そのためには信用情報機関での調査と、法律・税務両面からの検討が不可欠です。



不安があるときは、早めに税理士のような専門家に相談することが、最も確実で安心な一歩となりますよ。