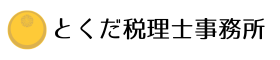面談予約専用ダイヤル044-712-0945
(電話受付:平日午前9時~午後6時)
出木栖木家の知的相続①:知的資産とは何か──数字に現れない「遺産」

登戸の税理士・まゆが綴る、出木栖木(できすぎ)家の物語。
文化と学問を受け継ぐ家に生まれた青年・学(まなぶ)が、
「数字に現れない遺産」と向き合うことで見えてきた、
相続のもうひとつの形。
登戸の街は、冬の名残りをまだ手放せずにいた。
多摩川の風は冷たく、遠くで鴨の声がかすかに響く。
駅前のざわめきを抜け、川沿いを少し歩いた先にある小さなカフェ。
その窓際の席で、学(まなぶ)くんは湯気の立つカップを両手で包んでいた。
「父が、遺言書を書こうとしてるんです。」
彼は静かにそう切り出した。
王禅寺の丘にある家からここまで来る途中、
白梅がちらほら咲き始めていたらしい。
季節は、冬と春の境をゆっくり渡っている。
「もうそんな年齢なのね。」
私は笑いながら答えた。
「ええ。でも最近、“書きっぱなしのまま終わるのは嫌だ”って言うんです。
論文もノートも途中で途切れてるものが多くて、
“どこかで一区切りをつけたい”って。」
登戸で相続専門の税理士事務所を開いている私は、
学くんにとっては遠い親戚のお姉さんのような存在だ。
税の話をしていても、どこか家族の会話に似ている。
「らしいわね、典さんらしい。」
彼の父は文化社会学の教授。
長く大学に勤め、いまは非常勤で学生を指導している。
最近は、自宅で研究ノートの整理をしているそうだ。
学問の話をするとき、彼の目元はよく父親に似ている。
「おじいちゃんの相続のとき、
そういうものも“財産”になるのかなって思ったことがあるんです。」
学くんは少し考えるように言った。
「祖父はこの地域の歴史を研究していて、
家の一角に資料を広げて使っていた和室がありました。
畳の上に古い地図や郷土資料のノートが積まれていて、
紙の匂いがずっと残っていたのを覚えています。」
外の光が少し傾き、カップの影がテーブルの木目に重なる。
その影のゆらぎの中で、彼の言葉が静かに続いた。
そのころ、彼はまだ小学生だった。
冬の終わりの、曇りがちな午後。
空気の底には、まだ冷たい土の匂いが残っていた。
祖父の家は、新百合ヶ丘の住宅街のはずれにあった。
再開発の波から少し離れた一角で、
古い畑と団地がまだ隣り合っていたころだ。
家の奥には、祖父が研究用に使っていた八畳の和室があった。
畳の上には、地図、郷土資料のノート、古い写真、
そして万年筆やルーペのような道具が散らばっていた。
彼はそこで、紙の匂いとインクの跡を覚えている。
親戚が集まり、遺品を整理していた。
父は一冊のノートを手に取り、
「お父さんの研究の跡だな……これは、相続の“財産”とは言えないけれど、残しておこう。」
とつぶやいた。
その言葉が、幼い彼には妙に印象に残った。
大切に見えるものと、そうでないもの。
その線を、誰が引くのだろう。
——税法でいう「財産」と、
人が心の中で思う「財産」は、重なっているようで、まったく別のものだ。
登戸で相続税専門の税理士事務所をしている私は、その違いを仕事のたびに感じる。
お客さまに「これはもう捨ててもいいですか?」と尋ねられるたびに、
その声の奥にためらいを聞く。
税務の視点では答えは明確でも、
人の記憶には“評価不能な価値”がある。
相続税法上の財産とは、
“金銭に見積もることができる経済的価値”のあるもの。
土地、建物、有価証券、著作権、特許権──。
それ以外の、思い出や信頼、そして知識や思想は、原則として課税の対象にはならない。
こうした“数字にできない遺産”を、社会学者のブルデューは“文化資本”と呼んだ。
家が受け継いできた教養や人脈、ものの考え方──
それもまた、世代をつなぐひとつの資産である。
「おじいちゃんの和室を片づけたとき、
父が“調査ノートや手紙は持って行っていい”って言って、
僕はいくつかもらったんです。」
学くんが笑った。
「今も部屋にあります。
古い紙に地名とか人の名前がたくさん書いてあって、
何を調べていたのかは分からないけど、
文字の形がきれいで、捨てられなくて。」
私はうなずいた。
相続というのは、財産を分ける手続きであると同時に、
“記憶をどう扱うか”を決める儀式でもある。
和室のノート、蔵書、手紙。
税務署の目には映らないけれど、
家族の心のなかでは確かに“遺産”として生きている。
学くんはしばらく黙っていた。
窓の外を行き交う人々を眺めながら、
「おじいちゃんの知識は、たぶん“もの”としてじゃなくて、
生き方の形で僕に残ってるのかもしれませんね。」
とつぶやいた。
私は微笑んで答えた。
「そう。だから、あなたがその思考をどう使うかが、
次の世代の“相続”なのよ。」
少し間をおいて、学くんが言葉をつないだ。
「父のほうは、もう“知が形になっている”気がします。
本も出していて、いまも印税が少し入っているみたいです。
おじいちゃんのノートとは、また違う形の“知の遺産”ですよね。」
「なるほど。」私はカップを置いた。
「じゃあ、次はその“形になった知”の話ね。」
知識や思想は課税できません。
けれど、社会の中でその価値が貨幣に変わる瞬間があります。
それが著作権や印税という“知的財産”です。
次回は、その境界について見ていきましょう。
💬 After Talk|あとがきトーク
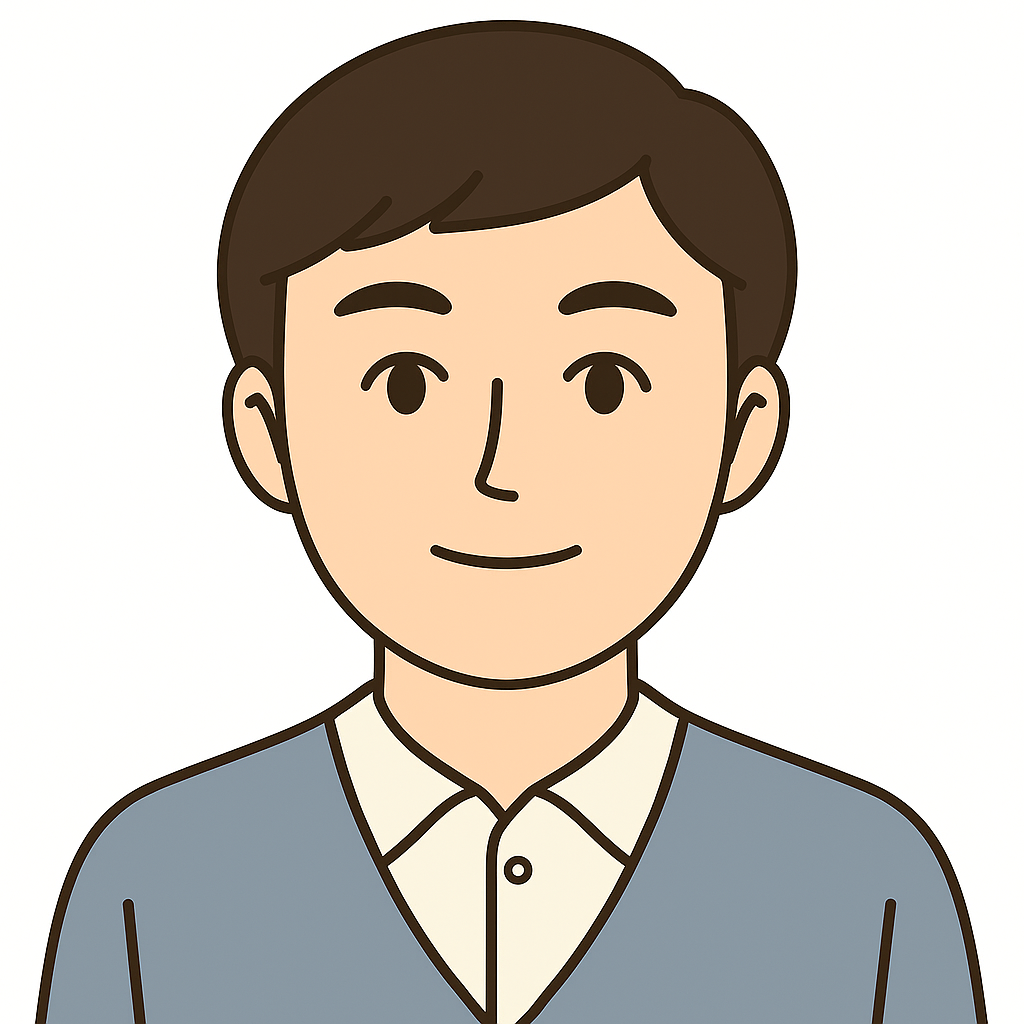
“評価できない財産”って、なんか不思議ですね。
価値がないんじゃなくて、数字にできないだけなんだなって。



そう。制度の外側にあるからこそ、人の心に残るの。
税金では扱えないけれど、ちゃんと“受け継がれる”のよ。
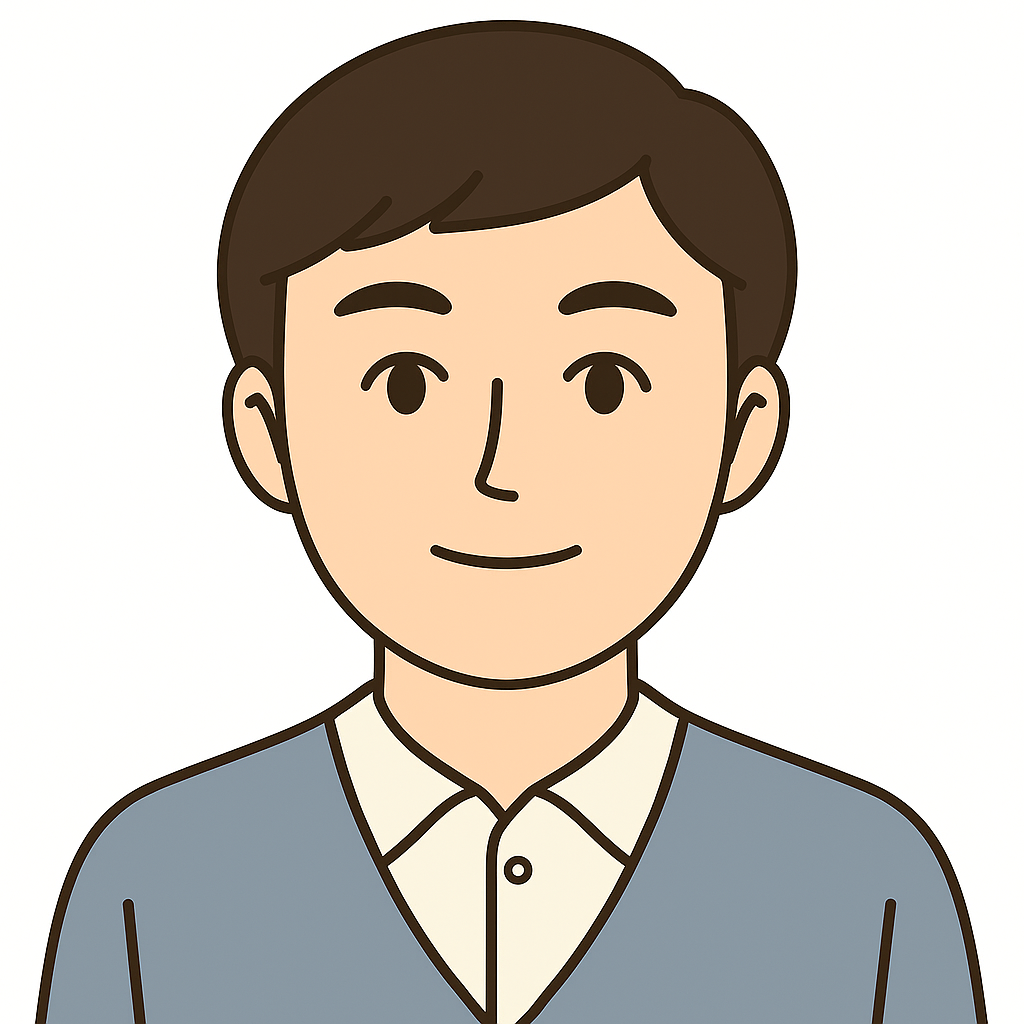
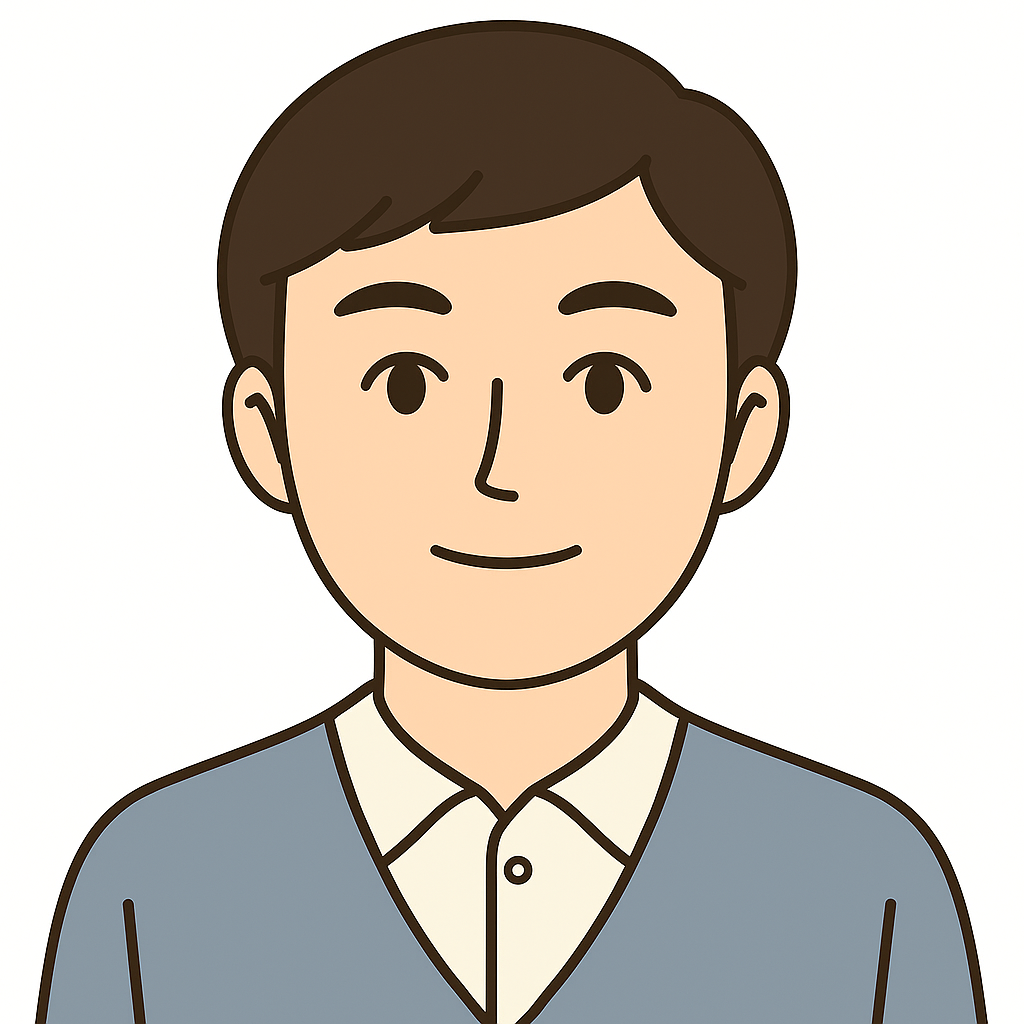
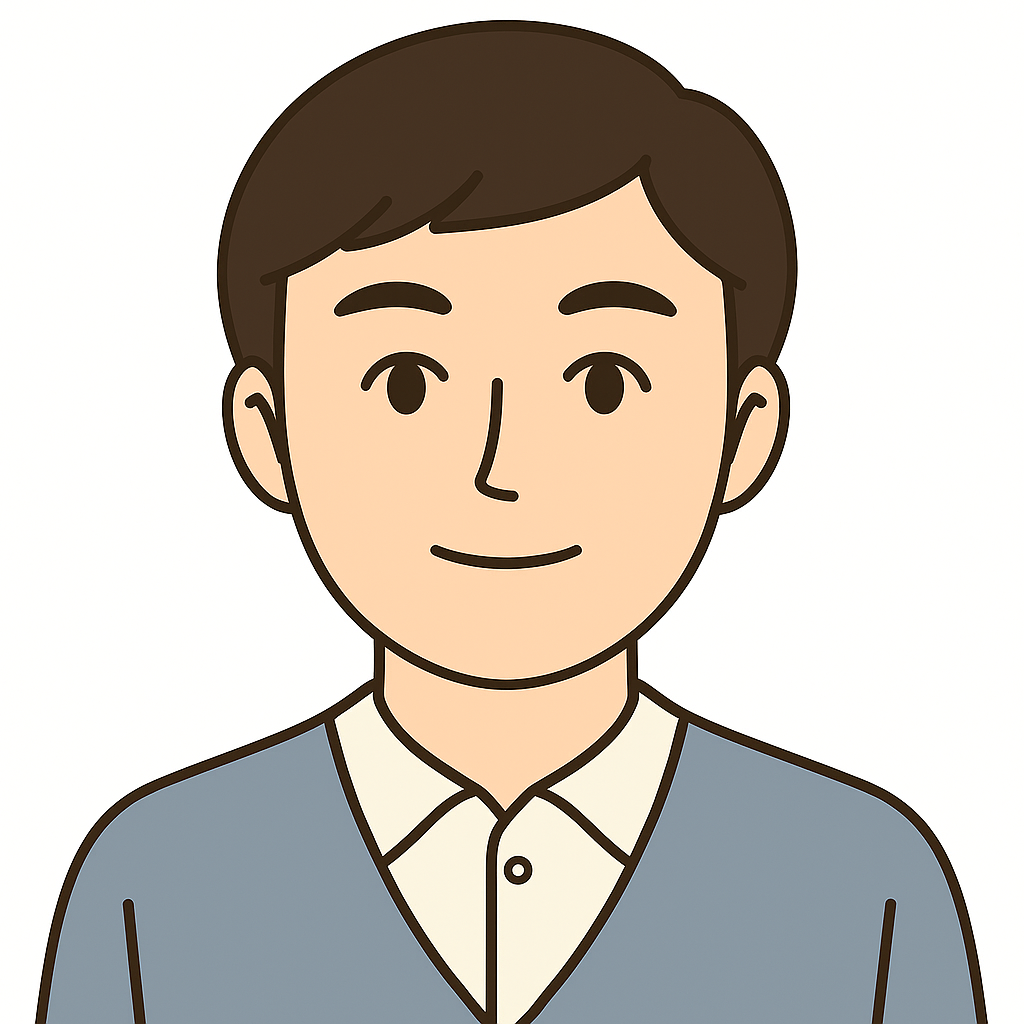
じゃあ次は、数字に現れるほう──著作権とか印税の話ですね。



そう、いよいよ“知が形になる瞬間”の相続。次回はそこへ行きましょう。
※本シリーズ「出木栖木家の知的相続」は、
教育・啓発を目的としたフィクションです。
登場する人物・団体・事例はすべて架空であり、
実在の個人・組織・事案とは関係ありません。
税務・法務の内容は一般的な解説を目的としたものであり、
実際の手続きや判断には、専門家へのご相談をおすすめします。